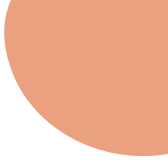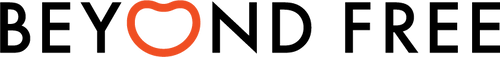プラントベースはミネラルを多く含む?種類やおすすめの食品を紹介

プラントベースの食品には、植物由来のミネラルが多く含まれています。植物性食品をバランスよく摂取していれば、ミネラルが不足する心配は少ないとされています。ただし、中には過剰摂取により問題が生じるミネラルもあるため、注意しましょう。
この記事では、ミネラルの種類を解説したうえで、ミネラルを多く含むプラントベースの食材を紹介します。
プラントベースとは?
明確な定義があるわけではないものの、プラントベースとは、植物性食品でできている食品などを食生活の中心にする考え方だと言われています。
プラントベースの食生活のために、肉、牛乳、卵といった動物性食品の代わりになる加工食品が作られています。その原材料は、大豆や小麦などです。
ミネラルとは?
ミネラルとは、体を構成する主要な元素である酸素、炭素、水素、窒素以外をまとめた総称です。ミネラルは、無機質とよばれる場合もあります。
ミネラルは、体の成長をサポートしたり、調子を整えたりする役割を果たしています。体内では合成できないため、必要な量を食事から体に取り込まなければなりません。ミネラルの過不足が生じた場合、不調や中毒が発生する可能性があります。適量のミネラルを摂取できるよう、日頃から食事のバランスを意識しましょう。
なお、ミネラルには多量ミネラルと微量ミネラルがあります。それぞれの詳細を解説します。
プラントベースフードとミネラルの関係
植物性食品でできている食品などには、植物由来のミネラルが多く含まれています。
ただし、ミネラルの種類は幅広いため、食べる食品の種類が偏ると摂取するミネラルの種類にも偏りが生じる恐れがあります。ミネラルの種類ごとに役割や効果が違うため、注意が必要です。
幅広い食材を選び、バランスの良い食事を心がけましょう。
ミネラルの種類

すでに説明したとおり、ミネラルは多量ミネラルと微量ミネラルに分かれています。それぞれには、具体的にどのようなミネラルが該当するのでしょうか?以下でくわしく解説します。
多量ミネラル
多量ミネラルとは、カルシウム、ナトリウム、リン、マグネシウム、カリウムのことです。それぞれのミネラルの特徴について説明します。
カルシウム
カルシウムは、骨や歯を構成するミネラルです。カルシウムが不足すると骨の成長に支障をきたし、骨粗鬆症を引き起こす恐れがあります。カルシウムは人の体に存在するミネラルの中で最も多く、体重の1~2%を占めています。
ナトリウム
ナトリウムは、体内の浸透圧を調整する役割を果たしているミネラルです。細胞の外の体液(細胞外液)に含まれています。
ナトリウムを摂取しすぎると、むくみが生じたり口が渇いたりする原因になります。また、高血圧や胃がんなどのリスクも高まるため、注意しましょう。
カリウム
カリウムも、体内の浸透圧を調整する役割をもつミネラルです。ナトリウムを排出する効果があり、とりすぎた塩分を調整できます。カリウムのほとんどは細胞内に含まれていますが、血液やリンパなどの体液や骨にも一部含まれています。
リン
リンは、体内のさまざまな細胞に存在しているミネラルです。多すぎるとカルシウムの吸収を阻害するため、摂りすぎには注意しましょう。加工食品やインスタント食品の中には、リンを多く含む食品もあります。
マグネシウム
マグネシウムは、ほとんどすべての生合成反応や代謝反応に必要なミネラルです。一般的な通常の食事をしていれば、マグネシウムが極端に不足する心配はありません。ただし、過剰摂取は下痢の原因になります。
微量ミネラル

微量ミネラルとは、鉄、銅、亜鉛、ヨウ素、モリブデン、クロム、マンガン、セレンのことです。それぞれのミネラルの特徴について説明します。
鉄
鉄は、赤血球のヘモグロビンに多く存在するミネラルです。成人の体内にある鉄の量は、約3~5gです。鉄が不足すれば「鉄欠乏性貧血」になり、集中力の低下、頭痛、食欲不振などの症状が出る恐れがあります。
銅
銅は、たんぱく質と結合して生体内反応の触媒として働くミネラルです。骨、骨格筋、血液に存在します。一般的な通常の食事をきちんと摂取している場合、銅が不足するケースはあまりありません。
亜鉛
亜鉛は、細胞の成長や分化に関わるミネラルです。すべての細胞に存在しています。亜鉛が不足すれば、味覚障害、皮膚炎、食欲不振といった症状が出る恐れがあります。
ヨウ素
ヨウ素は、甲状腺に存在し、甲状腺ホルモンを構成しているミネラルです。ヨードとよばれる場合もあります。日本では海産物を多く食べる習慣があるため、一般的な通常の食事で不足する心配はあまりありません。ヨウ素の摂取を目的とするサプリメント類を使用する場合は、むしろ過剰摂取に注意が必要です。
モリブデン
モリブデンは、酸化還元反応を触媒するモリブデン酵素を構成するミネラルです。一般的な通常の食事で必要な量を十分摂取できます。モリブデンは毒性が低いため、過剰摂取によって問題が生じる可能性も低いです。
クロム
クロムは、糖質代謝、コレステロール代謝、結合組織代謝、たんぱく質代謝などに関与しているミネラルです。体内に存在しますが、極微量です。
マンガン
マンガンは、酵素を活性化させる働きをもつミネラルです。また、金属酵素の構成成分となっています。体内の組織全体に分布しており、ミトコンドリア内に特に多く含まれています。
セレン
セレンは、体内の酵素やたんぱく質の一部を構成しているミネラルです。一般的な通常の食事を摂っていれば、不足する心配はありません。必要量と中毒量の差が小さいため、サプリメントによる過剰摂取には要注意です。
ミネラルを多く含むプラントベースの食材

ミネラルを多く含むプラントベースの食材としては、豆、野菜、海藻、主食となる穀物があげられます。今回はそれぞれ具体的にどのような食材が該当するか解説します。
豆
豆は、さまざまな種類のミネラルを含む食材です。100gあたりに含まれるミネラルの量をまとめると、以下のとおりです。
|
食材 |
ミネラルの種類 |
含有量 |
|---|---|---|
|
木綿豆腐 |
カルシウム |
93mg |
|
落花生 |
リン |
380mg |
|
絹ごし豆腐 |
マグネシウム |
50mg |
野菜・海藻
野菜や海藻も、ミネラルを豊富に含んでいます。100gあたりに含まれるミネラルの量をまとめると、以下のとおりです。
|
食材 |
ミネラルの種類 |
含有量 |
|---|---|---|
|
小松菜 |
鉄 |
2.8mg |
|
スイートコーン |
亜鉛 |
1.0mg |
|
刻み昆布 |
ヨウ素 |
230,000μg |
|
かぼちゃの種 |
クロム |
13μg |
主食となる穀物
主食となる穀物にも、ミネラルが多く含まれています。100gあたりに含まれるミネラルの量をまとめると、以下のとおりです。
|
食材 |
ミネラルの種類 |
含有量 |
|---|---|---|
|
そば(ゆで) |
モリブデン |
11μg |
|
玄米めし |
マンガン |
1.04mg |
|
発芽玄米めし |
亜鉛 |
0.9mg |
|
マカロニ・スパゲッティ(ゆで) |
銅 |
0.14mg |
プラントベースフードでミネラルを摂取しよう

ミネラルにはさまざまな種類があり、それぞれが体にとって重要な役割を果たしています。また、植物由来の原材料でできているプラントベースフードには、ミネラルが多く含まれているものがあります。
そのため、プラントベースの食生活を取り入れてバランスの良い食生活を送れば、体にとって必要なミネラルを毎日の食事でしっかり補給することが可能です。特に豆、野菜、海藻、穀物などには、ミネラルが多く含まれています。
BEYOND FREEでは、動物性原材料不使用の食品も多く扱っています。プラントベースフードを中心とした食生活をする際は体に必要なミネラルを摂取するために、ぜひ活用してください。
参考文献
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 文部科学省
e-ヘルスネット 厚生労働省 参照年月日:2023年12月19日
鉄 | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)
カルシウム | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)
ミネラル | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)
ナトリウム | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)
カリウム | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)
リン | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)
マグネシウム | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)