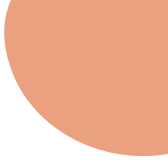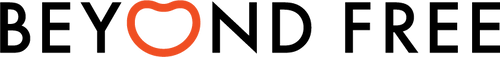長寿地域ブルーゾーンとは?沖縄以外の地域や食事の共通点などを解説

「健康で長生きしたい」という思いは多くの方が持つ願望ではないでしょうか?世界には100歳を超えても元気に暮らしている方が多い地域「ブルーゾーン」が5カ所あり、そこでの食生活には共通点が見られます。
この記事ではブルーゾーンの食生活の特徴について紹介するので、ぜひ参考にしてください。
ブルーゾーンとはどう言う意味?どこの地域を指す?

ブルーゾーンとは100歳以上の方が多く暮らす地域を意味する言葉で、アメリカの研究者・作家・探検家であるダン・ビュイトナーが提唱した考え方です。彼は自著「The Blue Zones 2nd Edition 世界の100歳人に学ぶ健康と長寿9つのルール」の中で「100歳人が多く暮らす世界の5カ所の長寿地域」として、以下の5カ所を挙げています。
-
日本・沖縄
-
イタリア・サルデーニャ島
-
ギリシャ・イカリア島
-
アメリカ・カリフォルニア州のロマリンダ
-
コスタリカ・ニコジャ半島
ブルーゾーンの食文化に見られる共通点について、次で見ていきましょう。
ブルーゾーンの住人が長寿である共通点

ブルーゾーンに共通して見られるライフスタイルは主に次の9つです。
-
適度な運動をする習慣:有酸素運動・バランス運動・筋力トレーニングを組み合わせて毎日行う
-
食事は腹八分・カロリー控えめ:必要以上に食べないための工夫をする
-
植物性食品を摂取する:野菜、豆類、全粒の穀類、ナッツなど
-
適量の赤ワインを飲む:1日にグラスで1~2杯
-
明確な目的を意識する:生きがいや人生の目的を持つ
-
ゆったりとした生き方を心掛ける:時間のゆとりを持つ、瞑想(めいそう)するなど
-
信仰を大切にする:宗教を問わず崇拝する
-
家族を何よりも大切にする:家族と過ごす時間を優先する
-
人とのつながり(社会的なつながり)を保つ:日常生活の中で良い人間関係や交流を保つ
この中で食事に関する2つについて具体的に見ていきます。
植物性食品の摂取が関係する理由
植物性食品とは上で挙げた穀類や野菜、豆類、ナッツの他に海藻や芋、きのこなども指します。これらの食品に含まれる機能性成分は、抗酸化機能などを持つフィトケミカルや便の排せつ機能を促す食物繊維などです。
このような健康維持に役立つとされる成分を日常的に摂取する食習慣によって長寿につながる可能性があります。フィトケミカルや食物繊維について、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
地中海食とは?特徴や健康効果とデメリットなど
赤ワインの適度な摂取が関係する理由
ぶどうの果皮や種子は抗酸化作用を持つ機能性成分ポリフェノールを多く含む食品のため、赤ワインを適度に摂取する食習慣が健康と長寿につながっていると考えられます。
ちなみに赤ワインはブドウの果実を丸ごと使って作られるため、果皮や種子を除去して作られる白ワインよりも多くのポリフェノールを含みます。
ブルーゾーンの食生活の特徴

ブルーゾーンの食生活には上記のような共通点があるものの、それぞれの具体的な食事内容は異なっています。ここでは各地域の食事内容と特徴について見ていきましょう。
沖縄(日本)
沖縄はアジアで唯一、ブルーゾーンに選ばれている地域です。沖縄には昔から健康的な食材を活かして作られる料理を「ヌチグスイ(命の薬)」「クスイムン(薬になる食物)」と呼んでいました。
「栄養豊富な食事は命の源であり、食生活を大切にすることが健康維持と病気予防につながる」と言った考え方があるためです。このように沖縄の伝統的な食文化には医食同源の概念が根付いています。
また沖縄の平均寿命は1980年の国勢調査で男女共に全国第1位でした。その長寿の原因として、1995年の研究・分析で低カロリー・低塩などの食生活が挙げられています。
しかし2000年以降は食生活の欧米化や肥満、運動不足などによって沖縄の平均寿命は男女とも下がってしまいました。
そこで沖縄県は再び健康地域になるように対策を講じ「今より10分多く歩く、週1回はお酒を飲まない日を作る、朝食を食べて、あぶらを控えた野菜たっぷりのごはんにする」などの健康増進の指針を作成しています。
ここからは長寿の地域になった沖縄の伝統的な食文化の8つの特徴について見ていきましょう。
①芋文化
1605年に中国から伝わった芋は食料として重宝し、カロリー源だけでなくビタミンCや食物繊維、カリウム、カルシウムなどの栄養素の補給源にもなりました。
当時は芋の葉を野菜として日常的に食べていたり、芋の葉か大根葉・薬草などが入った味噌汁と芋を合わせて食べたりしていた点が栄養学的に評価されています。
②豚はじめ肉食文化
沖縄では仏教の伝来が遅かったため肉食禁止の影響があまりなかったことと豚の飼料となる芋が伝来したことにより、豚の飼育が普及しました。
また東南アジアなどの熱帯的な食文化の影響を受けたり稲作文化の遅れがあったりした理由から肉類を多食する文化が根付き、そして、豚を余すところなくすべて食べる文化が長寿につながる栄養源と考えられています。
③豆腐文化
沖縄の豆腐は島豆腐と呼ばれ、本土の木綿豆腐と製法や含有する栄養成分などが異なります。島豆腐は特にたんぱく質や不飽和脂肪酸、リン・鉄などのミネラル、ビタミン類が多く、簡単に言うと水分量が少ない分、栄養が濃縮されている豆腐です。
その島豆腐を1980年代の沖縄では全国値よりも約30%も多く毎日食べていた点が長寿食のポイントとして挙げられています。
④野菜と野草・薬草文化
1990年前後において沖縄の方は緑黄色野菜を全国値よりも約30〜40%多く食べていました。それはビタミンCが多い島野菜(ゴーヤー、パパイヤなど)を多く食べたり、食物繊維や機能性成分を含む場合が多い野草・薬草(フーチバー/よもぎ、ンジャナ/苦菜など)を食べたりする文化があるからと考えられます。
⑤海藻文化
沖縄では沖縄独特のアーサやおきなわもずく、昆布を常食しています。特に昆布は豚肉と相性が良かったことと、だし利用だけでなく昆布そのものを食べる文化があったことなどから多用されていました。
昆布には13種類ものミネラルが含まれている他、食物繊維やフコイダンなどの機能性成分が含まれており、沖縄長寿に良い影響を与えたと考えられています。
⑥少ない食塩
沖縄では食塩や醤油の利用、漬物が少なく1982〜2003年の食塩摂取量は全国よりも約2g低いです。
これは沖縄の豚肉料理では食塩や醤油で味付けするのではなく油脂を利用する点や野草・薬草がふんだんにあり野菜を保存する必要もない理由から漬物を食べる習慣がない点、塩干しした魚介類を焼いて食べる習慣がない点などが理由と考えられています。
⑦乾物食文化
沖縄の保存食は前述した漬物や塩干しなどの塩蔵物ではなく昆布、かんぴょうなど乾物を活用していたことがヘルシーな料理につながっていたと考えられています。
⑧黒砂糖など地産地消の食材利用
沖縄はサトウキビの生産地にも関わらず1994年における砂糖の購入量は全国値の約90%と低めになっています。その理由は豚肉料理の調味料として砂糖を使わなかったためです。
砂糖の過剰摂取は問題であるものの、さんぴん茶と黒砂糖を食べる習慣もあり、それが沖縄の方の元気の源となっていました。
サルデーニャ島(イタリア)
サルデーニャ島の食生活は主に酸味のある全粒パンと野菜(ズッキーニやトマト、じゃがいも、なす、そら豆、ひよこ豆など)や羊から作られるペコリーノ・ロマーノチーズなどで肉を食べるのは週に一度、またはお祭りの時だけです。地中海エリアの基準からしても粗食と言えます。
またフラボノイドが一般的な赤ワインの2~3倍含有すると言われる地ワインや健康への影響が研究されているやぎの乳もサルデーニャ島の食文化に特徴的と言われています。
イカリア島(ギリシャ)
古代ギリシャ時代から保養地として知られていたイカリア島の食生活は野菜や豆、果物、オリーブオイルを多用します。
これらは地中海料理としては一般的なものですが、肉や魚の摂取量が少なく野菜が多い点が特徴です。朝食にやぎの乳も飲んだり、適量のワインやハーブティーも楽しんでいたりします。
ロマリンダ(アメリカ・カリフォルニア州)
ロマリンダには20世紀初頭から、菜食主義・禁酒・禁煙を教義とするセブンスデー・アドベンチスト教会の信者が多く住むようになりました。彼らが主に食べるものは野菜や果物、全粒穀物や豆類、乳製品です。
一方、4つ足の獣肉は禁止されており、鶏肉や魚は種類によっては食べても良いとされています。また夕食を軽めに早い時間帯に食べる、間食としてナッツを食べる、多量の水を飲むなどの行動もロマリンダの食生活の特徴です。
ニコジャ半島(コスタリカ)
ニコジャ半島に住む100歳の方々は全粒穀物やとうもろこしと豆が主体の伝統的な食生活をしており、他には乳製品、野菜、木の実やナッツなども食べます。それに対し、肉はほとんど食べません。
また十分な朝食に対して昼食と夕食は控えめに食べる、夕食は早い時間帯に食べる、マグネシウム含有量の多い硬水を飲むなどの行動もニコジャ半島における食生活の特徴です。
ブルーゾーンの食事には今すぐ始められる共通点がある!

ブルーゾーンの食事には全粒穀物や野菜、豆、ナッツなど植物性の食品が中心で肉や魚の摂取量は少なめという共通点があります。他には適量のお酒(ワインならグラス2杯程度)を飲むことや夕食を早い時間帯に軽めに取ること、水分摂取もブルーゾーンの特徴です。
植物性食品には長寿につながるものが多いと言って良いでしょう。今すぐ始められるものもあるので、毎日の食事で意識してみてはいかがでしょうか?
参考文献
Reライフ.net 朝日新聞 参照年月日:2024年12月6日 https://www.asahi.com/relife/
植物の力でより健康に!話題のフィトケミカル 山梨県厚生連 参照年月日:2024年12月6日 https://www.y-koseiren.jp/column/topic/3242
食物繊維の必要性と健康 e-ヘルスネット 厚生労働省 参照年月日:2024年12月6日 https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-05-001.html
平成21年(2009年) 第 5回 沖縄県議会(定例会)第 4号 10月 1日 福祉保健部長(奥村啓子) 参照年月日:2024年12月6日 https://www2.pref.okinawa.jp/oki/Gikairep1.nsf/481e05e7edaca1db49256f540004c033/d6352b1b8cc3cbb24925777c000dd1c3?OpenDocument
ブドウとワインに含まれるポリフェノール類の健康効果 農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター 参照年月日:2024年12月6日 https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010921290.pdf