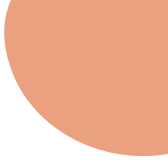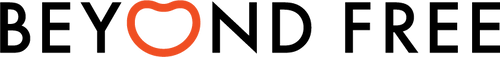LDL(悪玉)コレステロールを下げる食事とは?今日からできる具体例もご紹介

「LDL(悪玉)コレステロールを下げたいけれど、何から始めたらいいの?」などと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?高LDL(悪玉)コレステロールは、生活習慣病である脂質異常症の指標の一つでもあり放置すると重大な病気を引き起こすリスクがあります。
この記事では、LDL(悪玉)コレステロールを下げるための具体的な食事方法についてご紹介します。無理なく続けられる方法でご自身の食生活を見直していきましょう。
コレステロールとは

コレステロールは摂らない方が良いイメージがあるかもしれませんが、実は私たちの体になくてはならない脂質の一種です。細胞膜を構成したり、ホルモンや胆汁酸を作る材料になったりと多様な役割を担っています。
コレステロールには「LDL(悪玉)コレステロール」と「HDL(善玉)コレステロール」があり、この2つのバランスが大切です。血液中で過剰もしくは不足した場合、脂質異常症などの原因になることがあります。
LDL(悪玉)コレステロールとは
LDL(悪玉)コレステロールは肝臓にあるコレステロールを体全体に運ぶ役割を担っています。余分なコレステロールを血管壁に蓄積させてしまう性質を持っていることから「悪玉コレステロール」とも言われています。
LDL(悪玉)コレステロールが過剰になると血液中の脂質のバランスが崩れて脂質異常症につながる可能性があるため、脂質異常症の診断基準以下に抑えておくことが大切です。
HDL(善玉)コレステロールとは
HDL(善玉)コレステロールは血管壁にたまったコレステロールを肝臓に運ぶ役割を担っています。血液中の余分なコレステロールを回収する働きがあることから「善玉コレステロール」と言われています。
HDL(善玉)コレステロールはLDL(悪玉)コレステロールと反対に、少なくなり過ぎると脂質異常症につながるリスクが高くなります。そのためHDL(善玉)コレステロールは脂質異常症の診断基準以上にすることが重要です。
脂質異常症になる基準値

脂質異常症とは、血液中の脂質バランスが崩れてしまう状態を指します。この状態が進むと動脈硬化が促進され、心筋梗塞や脳卒中などの重大な病気を引き起こすリスクが高まります。
診断基準値はLDL(悪玉)コレステロールが140mg/dL以上、HDL(善玉)コレステロールが40mg/dL未満の他、トリグリセライド(中性脂肪)が10時間以上の絶食状態で150mg/dL以上、もしくは10時間以上の絶食が確認できない場合で175mg/dL以上、Non-HDLコレステロール*が170mg/dL以上です。
*Non-HDLコレステロールとは総コレステロールからHDL(善玉)コレステロールを引いた値
LDL(悪玉)コレステロールを下げる食事方法とは

ここからLDL(悪玉)コレステロールを下げる食事をご紹介します。ただし、LDL(悪玉)コレステロールを下げる食事の対策でHDL(善玉)コレステロール値を上げることにはならない点と食事だけでなく運動も大切である点にご留意ください。
飽和脂肪酸の摂取量を減らす
飽和脂肪酸の過剰摂取は、LDL(悪玉)コレステロール値を上昇させる主な原因の一つです。飽和脂肪酸の摂取はコレステロールの摂取よりも影響が大きいと言われているため、まずは飽和脂肪酸を多く含む食品を控えることから始めましょう。以下に具体的な方法を紹介します。
肉類を魚介類・大豆製品に替える
肉類には飽和脂肪酸が多く含まれていることが以下の表からも読み取れます。そこで肉類よりも飽和脂肪酸が少ない魚介類や大豆製品に置き替えると、飽和脂肪酸の摂取量を削減できます。
|
食品 |
飽和脂肪酸 |
|
木綿豆腐 |
0.79g |
|
ぎんざけ/養殖/生 |
2.30g |
|
まだい/養殖/皮つき/生 |
2.26g |
|
うし/もも/脂身つき/生 |
5.11g |
|
ぶた/もも/脂身つき/生 |
3.59g |
|
にわとり/もも/皮つき/生 |
4.37g |
※すべて100gあたりの量
※出典:文部科学省|日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
例えばハンバーグや焼肉などの肉料理を多く摂取する方は、刺身や焼き魚などの魚料理に替えてみる、または一部のミンチ肉を豆腐や大豆ミートで置き替えた豆腐ハンバーグにするなどの方法があります。
大豆ミートはブロックやスライス、フィレなど見た目や食感が本物の肉に似せて作られているため、炒め物や煮物など様々なレシピに活用できるのも魅力です。
大豆ミートについて詳しくは以下をご覧ください。
代替肉とは?どんな種類や商品があるのかをご紹介
肉類の脂肪部分を取り除く・脂肪部分が少ない部位を使う
肉類は脂身つきかや部位によって飽和脂肪酸の量が異なります。それぞれの肉・部位にどのくらいの飽和脂肪酸が含まれているのかみていきましょう。
■もも肉における脂身つきと赤身の飽和脂肪酸量の違い
|
食品 |
飽和脂肪酸 |
|
うし/もも/脂身つき |
5.11g |
|
うし/もも/赤肉 |
1.56g |
|
ぶた/もも/脂身つき |
3.59g |
|
ぶた/もも/赤肉 |
1.12g |
|
にわとり/もも/皮つき |
4.37g |
|
にわとり/もも/皮なし |
1.38g |
※すべて生、100gあたりの量
※出典:文部科学省|日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
■各部位における飽和脂肪酸量の違い
|
食品 |
飽和脂肪酸 |
|
うし/かた |
7.23g |
|
うし/ばら |
12.79g |
|
うし/もも |
5.11g |
|
ぶた/かた |
5.25g |
|
ぶた/ばら |
14.60g |
|
ぶた/もも |
3.59g |
|
にわとり/むね |
1.53g |
|
にわとり/もも |
4.37g |
※すべて生、脂身つき(鶏肉は皮つき)、100gあたりの量
※出典:文部科学省|日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
特に飽和脂肪酸は肉の脂身(霜降り/白い部分)やばら肉・ひき肉、鶏肉の皮などに多く含まれていることが数字でみると良く分かります。
また、かた肉、むね肉、もも肉などは脂肪分が少なめです。調理する際には鶏肉の皮を剥ぐ、牛肉や豚肉の脂身を切り落とす、ばら肉よりもかた肉を選ぶなどの工夫で飽和脂肪酸の摂取量を減らすことができます。
あぶらの種類を替える
飽和脂肪酸が多い肉類のあぶらを不飽和脂肪酸が多い植物性のあぶらに替えるのもおすすめです。肉類のあぶら(ラード、有塩バター)と植物性のあぶら(オリーブ油、ごま油、えごま油)の飽和脂肪酸量を比較すると、その量の差は歴然です。
|
食品 |
飽和脂肪酸 |
|
オリーブ油 |
1.99g |
|
ごま油 |
2.26g |
|
えごま油 |
1.15g |
|
ラード |
5.89g |
|
無発酵バター/有塩バター |
7.57g |
※すべて15g(約大さじ1杯)あたりの量
※出典:文部科学省|日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
具体的な対策として、普段使用する脂をごま油やえごま油などに替える、お菓子作りに使うラードやバターをオリーブ油などに替えると言った様々な方法があります。
また不飽和脂肪酸の中でも魚油に多く含まれるω-3(オメガ3)脂肪酸は、心血管系疾患のリスクを低下させるなど体に良い影響を与えることが知られています。
洋菓子を和菓子に替える
間食を減らす、あるいは無くすのは飽和脂肪酸を減らす上で理想的です。特に高いエネルギー(以下カロリー)の食事を頻繁に摂取している方や脂っこい料理を多く食べる方などは間食を控えることで健康リスクを減らせる可能性があるでしょう。
その上で食事における脂質の摂取量がそれほど多くない方や間食がしたいという方は、洋菓子から和菓子に替えて飽和脂肪酸の摂取を抑える方法もあります。
ただし和菓子は糖質が多いため、血糖値の高い方や甘い物・主食ばかり食べる方、1日の摂取カロリーが高い方にはおすすめできません。厚生労働省が推奨する間食の摂取カロリー量の目安は1日200kcalです。
|
食品 |
飽和脂肪酸 |
|
くし団子/みたらし |
0.13g |
|
大福もち/こしあん入り |
0.12g |
|
ショートケーキ/果実なし |
5.80g |
|
ドーナッツ/ケーキドーナッツ/プレーン |
3.70g |
※すべて100gあたりの量
※出典:文部科学省|日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
ドーナツやケーキなどの洋菓子は、生クリームやバターなどを多く使用するため飽和脂肪酸が多くなりがちです。一方で大福もちやくし団子などはあんこや餅などが主原料なので、飽和脂肪酸が比較的少ない傾向があります。
コレステロールの摂取量を減らす
前述の通り血液をサラサラにするためには飽和脂肪酸の削減が第一ですが、次に意識するべきなのはコレステロールの摂取量です。コレステロールは鶏卵の黄身や魚卵に多く含まれています。
魚卵には「イクラ」「めんたいこ」「たらこ」「かずのこ」「すじこ」などがあり、各々に含まれる飽和脂肪酸量は以下の通りです。
|
食品 |
飽和脂肪酸 |
|
しろさけ/イクラ |
2.42g |
|
しろさけ/すじこ |
2.72g |
|
すけとうだら/たらこ/生 |
0.71g |
|
すけとうだら/からしめんたいこ |
0.54g |
|
かずのこ/生 |
0.85g |
|
卵黄/生 |
9.39g |
|
卵白/生 |
微量 |
※すべて100gあたりの量
※出典:文部科学省|日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
コレステロールが気になる方は鶏卵や魚卵を摂取する量や頻度を減らして、魚やプラントベースの食品を取り入れるようにしましょう。
食物繊維の摂取量を増やす
食物繊維は血中コレステロール値の低下や血糖値の急激な上昇を抑える働きがあります。特にキャベツやごぼうなどの野菜類や、わかめや昆布などの海藻類、ぶなしめじやしいたけなどのきのこ類など食物繊維を多く含む食品を積極的に摂ることが大切です。
食物繊維には水溶性・不溶性があり、不溶性食物繊維が腸内環境を整えるのに役立ちます。
HDL(善玉)コレステロールを高くする方法とは

HDL(善玉)コレステロール値が低い原因には肥満、喫煙、運動不足などが挙げられます。減量や禁煙、運動を行いHDL(善玉)コレステロールを増やしましょう。
またアルコールの摂取もHDL(善玉)コレステロールを低下させる原因となり、高血圧や肝障害に影響する可能性があるため飲み過ぎには注意が必要です。
中性脂肪を下げる食事方法とは

中性脂肪とは肉類や魚類、食用油などの脂質や体内にもともと在る脂質の一つですが、過剰摂取により体脂肪として蓄えられます。
カロリーの摂り過ぎ、特に甘いものやアルコール、油もの、ソフトドリンク、糖質などの摂り過ぎが要因とされているため、中性脂肪を下げるためには糖質やカロリーを抑える食事と適度な運動を習慣づけるように心がけましょう。
LDL(悪玉)コレステロールを下げる食事はできるところから始めよう!

LDL(悪玉)コレステロールを下げるための食事改善は、無理なくできるところから始めることが大切です。まずは飽和脂肪酸を多く含む肉類を控えて、魚類や植物性の食品を活用した食事を楽しみましょう。
参考文献
eヘルスネット 参照年月日:2024年9月22日
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/
【監修者】
管理栄養士・和食ライフスタイリスト
合田 麻梨恵

大学卒業後、コンビニ商品開発を経て独立。2万件以上の予防医学に関する論文読破・発酵生産者100軒以上訪問・100名様以上の栄養指導経験から”令和の和食TM”で未病のない身体づくりを推進中。一般社団法人日本和食ライフスタイリスト協会代表理事、「中高年のための食と予防医学」の著者。