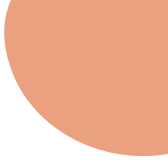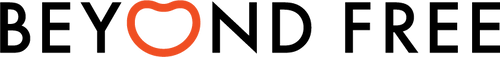植物性プロテインって?動物性との違いや種類、メリットなど

植物性プロテインとは、どんなものかご存じでしょうか?プロテインは大きく植物性と動物性の2つに分類でき、それぞれ原料や特徴が異なります。
この記事では植物性プロテインの種類や動物性プロテインとの違いについて解説しています。植物性プロテインのメリットを知って、毎日の食生活に取り入れてみましょう。
植物性プロテインとは

プロテインには植物性たんぱく質を原料とするものがあり、植物性たんぱく質は英語で「vegetable protein」と表現します。植物性たんぱく質として挙げられるのは、ソイ(大豆)、ピー(エンドウ豆)、ライス(玄米)、ヘンプ(麻の実)などです。
プロテインはたんぱく質を指し、炭水化物や脂質と並んで、エネルギー産生栄養素として重要な役割を持っています。たんぱく質は鎖状に連なったアミノ酸で構成され、20種類のアミノ酸が約50〜1,000個つながった化合物です。
良質なたんぱく質を含む食品
20種類あるアミノ酸の中で、ヒトが体内で作れない9種類を必須アミノ酸と言います。たんぱく質を合成するためには20種類のアミノ酸がすべて必要なため、必須アミノ酸は食事からの摂取が大切です。
良質なたんぱく質を含む食品は、たんぱく質の含有量が多く体内での利用率が高いものを指し、例えば肉や卵、大豆などが挙げられます。大豆は植物性食品ですが動物性食品に負けず劣らず良質なたんぱく質です。
動物性プロテインとの違い
大豆などの植物性食品に含まれている植物性たんぱく質に対して動物性たんぱく質は肉や魚、卵、牛乳・乳製品に含まれています。たんぱく質は原料となる食品によって呼び方が変わり、牛乳由来のものはホエイプロテインやカゼイプロテイン、大豆に由来するたんぱく質はソイプロテインと呼ばれます。
たんぱく質は種類により吸収速度に違いがあるのが特徴です。例えば、同じ牛乳由来でも、ホエイプロテインは消化吸収が速い一方、カゼイプロテインは消化吸収のスピードがゆっくりです。植物性のソイプロテインは、ゆっくり吸収されると言われています。
植物性プロテインの種類と特徴

植物性プロテインには種類があり、原料や特徴が異なります。ここからは主な3つの植物性プロテインの特徴を紹介します。
ソイ(大豆)
ソイプロテインは大豆を原料としてたんぱく質を取り出したプロテインです。食品に含まれる必須アミノ酸のバランスを数値化したものをアミノ酸スコアと言い、大豆はアミノ酸スコアが100であることから、植物性食品の中でもたんぱく質の質が高いと言えます。
ソイプロテインは、牛乳を原料とするホエイプロテインに比べて、消化吸収の速度が緩やかです。乳アレルギーや卵アレルギーの方は、たんぱく質を摂取するための代替として、ソイプロテインが一つの選択肢になるでしょう。
また大豆には機能性成分として知られるサポニンやレシチン、大豆イソフラボンが含まれています。以下の記事では大豆のたんぱく質について詳しく解説しています。
大豆のたんぱく質ってすごい?含有量や種類、大豆食品や野菜などとの比較
ピー(エンドウ豆)
インゲン豆などの腎臓に似た形をしている豆は一般的に英語で「Bean」と総称されますが、丸い球状の豆は「Pea」と呼ばれ、代表的なものはエンドウ豆です。エンドウ豆から作られた植物性のプロテインをピープロテインと言い、そのほとんどが黄エンドウ豆を原料としています。日本ではあまり馴染みがない一方、海外では日常的に食べられている食品です。
エンドウ豆には、その他に緑色の青エンドウ豆や褐色の赤エンドウ豆などがあり、黄エンドウ豆と同じエンドウ属ですが種類は異なります。また黄エンドウ豆は別名「白エンドウ豆」とも呼ばれています。
必須アミノ酸にはバリンやロイシン、トリプトファンなどの9種類があり、黄エンドウ豆は必須アミノ酸の中でもメチオニンが少ない食品です。そのためメチオニンの含有量が多い食品と組み合わせて食べると良いでしょう。
エンドウ豆は豆類ですが大豆とは種類が違うため、大豆アレルギーの方は代替として選択できます。乳・卵アレルギーを持つ方にも、おすすめです。
植物性たんぱく質を含む黄エンドウ豆は、スーパーフードと言われることもあります。スーパーフードについては、以下の記事で詳しくご覧いただけます。
スーパーフードを一覧で紹介!栄養価や特徴など
ライス(玄米)
玄米を原料とする植物性たんぱく質をライスプロテインと言います。玄米は精米されていない米のことを指し、精米の段階で取り除かれる胚芽や外皮(ぬか)を丸ごと残したものです。
玄米には、たんぱく質に加えてビタミンB群や食物繊維、ポリフェノールが多く含まれています。米の色が特徴的な赤米や黒米、紫米などを古代米と呼びますが、これらも玄米の一種です。玄米は乳・卵・大豆アレルギーの方の代替品として利用できます。
植物性プロテインのメリット

植物性プロテインを取り入れるメリットは、大きく2つ考えられます。植物性プロテインのメリットを知り、日々の食生活における良質なたんぱく源として活用してみてはいかがでしょうか?
誰でも楽しみやすい
植物性プロテインは大豆やエンドウ豆、玄米などの植物性食品を原料としているため、動物性食品を控える食習慣を持つベジタリアンやヴィーガンの方でも食べられます。
また動物性プロテインの中には牛乳を原料としたホエイプロテインや、卵白を含むプロテインもあり、乳・卵アレルギーの方は摂るのを控える必要があります。アレルギーを避けるための代替として、植物性プロテインが一つの選択肢になるでしょう。
環境に優しい
植物性プロテインは、環境に優しい食品と言う観点でも注目を集めています。動物性プロテインは牛が作り出す乳などを原料としており、家畜の飼育に資源を多く使うことから環境に与える負荷が大きくなります。
それに対して、植物性プロテインは家畜を飼育するのに比べて栽培や収穫に必要な資源が少ないのが特徴です。さらに原材料として使用された植物性の残渣は堆肥と言う形で再利用でき、ライフサイクル全体を通して環境への負荷を抑えられます。
植物性プロテインを選択することで家畜への過剰な食糧供給を抑え、食糧問題にアプローチできる可能性があるでしょう。植物性の食材だけで作られた食品はプラントベースフードと言われ、環境保護の側面から関心が高まっています。プラントベースフードについては、以下で詳しくご覧ください。
プラントベースフードはなぜ環境にやさしい?
植物性プロテインで地球に優しくたんぱく源を補給しよう!

植物性プロテインは、大豆やエンドウ豆、玄米などの植物性食品を原料に作られるプロテインです。植物性プロテインには動物性たんぱく質が含まれていないため、ベジタリアンやヴィーガンの方に適している他、乳・卵アレルギーの方でも食べられるのがメリットです。
環境にも優しい植物性プロテインを、たんぱく質の補給源として取り入れてみてはいかがでしょうか?
参考文献
e-ヘルスネット 厚生労働省 参照年月日2025年2月5日
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary
良質なたんぱく質を多く含む食品をとりましょう 独立行政法人 環境再生保全機構 参照年月日:2025年2月5日 https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/copd/nutrition/04.html
プロテインサプリメント JAPAN SPORT COUNCIL 参照年月日:2025年2月5日 https://www.jpnsport.go.jp/hpsc/study/sports_nutrition/tabid/1497/Default.aspx
食品たんぱく質の栄養価としての「アミノ酸スコア」 日本食品分析センター 参照年月日:2025年2月5日
https://www.jfrl.or.jp/storage/file/news_no46.pdf
良質なたんぱく質とは?【低栄養予防】 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 参照年月日:2025年2月5日
https://www.ncgg.go.jp/ri/advice/09.html
大豆及び大豆イソフラボンに関するQ&A 農林水産省 参照年月日:2025年2月5日
https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_daizu_qa/
豆の調理特性データブック 財団法人 日本豆類基金協会 参照年月日:2025年2月5日
https://www.mame.or.jp/Portals/0/resources/library/pdf_s/mamedatabook_all.pdf
Yellow Field Pea Protein (Pisum sativum L.): Extraction Technologies, Functionalities, and Applications 2023 Nancy D. Asen, Rotimi E. Aluko, Alex Martynenko, Alphonsus and Pankaj Bhowmik 参照年月日:2025年2月5日
https://www.mdpi.com/2304-8158/12/21/3978
お米を丸ごと味わう「機能性米」のススメ 農林水産省 参照年月日:2025年2月5日 https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/culture/wagohan/articles/2111/spe3_03.html