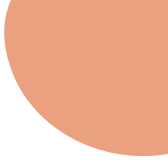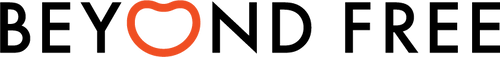内臓脂肪を減らす食事と実践のコツ

お腹周りに肉がついてきたのが気になるものの、運動しても中々続かない方は多いのではないでしょうか?生活習慣が原因でついてしまった内臓脂肪は、食事を改善して減らせるかもしれません。
この記事では、内臓脂肪が増える原因から減らす食事のポイント、無理な食事制限が必要のない実践のコツまで詳しく紹介しています。健康的な食生活で、内臓脂肪がつきにくい体を目指しましょう。
内臓脂肪とは|中性脂肪との違い

まずは、内臓脂肪がどのようなものなのか確認してみましょう。内臓脂肪とは体脂肪の一種であり、胃や腸などの臓器周りにつく脂肪のことを指します。皮下脂肪も体脂肪の一つとされ、こちらは下腹周りやおしりの皮膚の下につく脂肪です。
つまり、内臓脂肪と皮下脂肪を総称して「体脂肪」と呼んでいます。また中性脂肪と言う言葉を聞いたことがあると思いますが、中性脂肪は体内に存在する脂質の一種で、体脂肪を構成する成分です。
食事から摂取して消費されなかったエネルギー源は中性脂肪となり、中性脂肪が内臓脂肪や皮下脂肪などの体脂肪として脂肪細胞に蓄えられます。
内臓脂肪が増える原因

体内で内臓脂肪が増えてしまうのは、生活習慣が大きく影響していると言われています。以前までは「肥満は遺伝によるもの」と言う考え方が通説でしたが、近年は遺伝だけでなく、食習慣の変化や身体活動量の不足が肥満に関係していると考えられるようになりました。
食べ過ぎや運動不足によって摂取エネルギーが消費エネルギーを上回ると、消費されなかった過剰分のエネルギーが体脂肪として蓄積され、肥満につながるとされています。
内臓脂肪を減らすメリット

内臓脂肪を減らすことには、健康上のメリットがあります。肥満には「内臓脂肪型」と「皮下脂肪型」の2タイプがあり、特に内臓脂肪型肥満は糖尿病や脂質代謝異常、高血圧症、心血管疾患などにかかるリスクが高いと言われています。
内臓脂肪型肥満はこれらの生活習慣病だけでなく他の様々な疾患を発症する可能性が高いため、内臓脂肪を減らすことでそれらの疾患にかかるリスクの減少が期待できるでしょう。
肥満は単に体重が多いだけでなく体脂肪が過剰についた状態を指すため、内臓周りに脂肪が多く蓄積する内臓脂肪型肥満には特に注意しましょう。
内臓脂肪を減らす食事と実践のコツ

すでについてしまった内臓脂肪を減らすためには、食生活の見直しや継続的な運動が有効と考えられています。日頃の生活で適度な運動と栄養バランスの取れた食事を意識しましょう。ただし無理な食事制限をすると健康にも良くなく、続きません。そこで、ここからは内臓脂肪を減らしたい方に向けて食事のコツを紹介します。
健康的な食事や栄養素の摂り方については、こちらの記事もぜひご覧ください。
健康的な食生活とは?健康寿命延伸のための食事のポイントを解説
五大栄養素の3つの働きとは?6大・7大栄養素もある?
腹八分目で食事を止める
前述の通り摂取エネルギーが消費エネルギーを上回ると内臓脂肪がつきやすくなるため、カロリー過多にならないように腹八分目で止めるように心がけましょう。腹八分目で食事を終えると満腹になるまで食べるよりも摂取カロリーが減るので、内臓脂肪の蓄積を防ぐのに効果的です。
腹八分目のコツとしては、盛る器のサイズを小さくしたり一皿に盛る量を少なくしたりする方法が挙げられます。また一口食べるごとに箸を置くようにすると、ゆっくりとよく噛んで食べるようになり満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを防ぎやすくなるでしょう。
ゆっくり十分に噛んで食べる
食べるスピードが速いことを「速食い」と言いますが、疫学調査によると普段から速食いの方は肥満になりやすい傾向が見られます。中でも「速食い」と「お腹いっぱい食べる」習慣を両方とも持っている方は、特に肥満度が高い傾向です。
厚生労働省の検討会では、肥満対策の一つとして速食いの防止を図る「噛ミング30(カミングサンマル)」運動を提唱しました。これは一口ごとに30回噛む習慣を身につけると言う内容です。しかし実際に行うには難しいと考えられるため、あくまでも目安としながら十分に噛んで食べましょう。まずは自分が一口で何回噛んでいるか実際に数えて意識してみると良いかもしれません。
夜遅い食事は控える
内臓脂肪の蓄積を防ぐには夜遅い食事を控えることも大切です。夜間になると、体内では脂肪を蓄えて分解を抑える働きのあるBMAL1と言うたんぱく質が活性化されます。そのため夜に食事を摂ると脂肪が蓄積され、太りやすくなると言われています。
仕事で帰宅が遅くなる場合は、遅い時間の食べ過ぎに気を付けましょう。夕方頃におにぎりなどできる範囲で腹持ちの良い食品を摂り、家に帰ってからはサラダやスープなどの軽い食事に留めるのがおすすめです。
間食は食べても良いが全体の食事バランスで調整する
間食は食べても良いですが、食事とのバランスを考慮して全体の摂取カロリーが多くならないように調整が必要です。「食事バランスガイド」では1日あたりに摂るお菓子や嗜好飲料のカロリー量の目安を200kcalとしています。
ただしお菓子は炭水化物や脂質が多い一方で、ミネラルやビタミンなどの栄養素がほとんど含まれていません。そのため間食を摂る時は1日の食事の中でお菓子の割合が多くなりすぎないよう、全体のバランスを考えながら摂る必要があります。
アルコールを飲みすぎない
アルコールの過剰摂取は摂取エネルギーの増加につながります。なぜならアルコール1gあたり7.1kcalで、1gあたり9kcalの脂質よりもカロリーは低いものの、1gあたり4kcalの糖質やたんぱく質よりも高カロリーなためです。
厚生労働省の国民健康・栄養調査では「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」を次のように定義しています。
【1日あたりの純アルコール摂取量】
・男性 40g以上
・女性 20g以上
すなわち、この数値を上限に適度な飲酒を楽しむことが大切だと考えられます。なお純アルコール量とは飲んだお酒の量ではなく、お酒に含まれるアルコールの量です。
純アルコール量は、アルコール度数やアルコールの比重を考慮して算出されます。純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性で20g以上になる例を以下に挙げています。
【男性で40g以上になるケース】
・ビールのロング缶(500ml) 2本
・日本酒 2合
【女性で20g以上になるケース】
・ビールのロング缶(500ml) 1本
・アルコール度数7%の缶チューハイ(350ml) 1本
アルコールの摂り過ぎを防ぐためには1杯を純アルコール量の少ない種類に変えてみたり、飲み始めや途中に水を挟んでみたりと、できそうなことから少しずつ取り組んでみましょう。
野菜類・きのこ類・海藻類を意識する
野菜類・きのこ類・海藻類は低カロリーで、なおかつ食物繊維・ビタミン・ミネラルの補給源になります。食物繊維が多く繊維質な点から上述した「ゆっくり十分に噛んで食べる」にもつながるため積極的に摂るのがおすすめです。
野菜は1日350g取りましょうと目標量が設定されていますが、近年の食生活では一皿分の摂取量が不足していると言う指摘があります。より多くの野菜を取るため、普段の食事に野菜サラダやほうれん草のお浸しなど一皿分の野菜を中心とした副菜をプラスしてみましょう。
野菜類・きのこ類・海藻類を摂るポイントについては以下で詳しく解説しています。
野菜1日分の量350gとはどれくらい?無理なく摂取する方法などご紹介
きのこに含まれる栄養とその働きとは|おいしさと栄養を逃さない調理法も
海藻類の五大栄養素を比較!調理のコツと食べ方
調理法を意識する
料理のカロリーを抑えるためには、できるだけ油を使わない調理も推奨されます。炒め物や炒め煮、揚げ物は油による脂質でカロリーが高くなりがちなため、茹でる、蒸す、生などの調理法でカロリーを抑えましょう。
食材ごとに、カロリーを抑えられる調理法と高くなる調理法を以下で比較しています。
|
食材 |
カロリーを抑えられる調理法の例 |
カロリーが高くなる調理法の例 |
|
鶏もも肉 |
鶏の塩焼き | チキンカツ |
|
絹ごし豆腐 |
冷や奴 | 揚げ出し豆腐 |
|
なす |
焼きなす | なすの揚げ浸し |
カロリーの少ない食品選びを意識する
肉類・魚類は種類によって含まれる脂質の量に違いがあります。脂質が少ない食品を選んだり、あらかじめ脂質を取り除いてから調理したりとカロリーを少なくする工夫をすると良いでしょう。
肉類と魚類で脂質が少ないものと多いものをそれぞれ比較しているため参考にしてください。
|
食材 |
脂質が少ない |
脂質が多い |
|
肉類 |
鶏ささみ、鶏ひき肉、豚もも | サーロイン、牛ロース、豚バラ |
|
魚類 |
まだら、かれい、まぐろ(赤身) | トロ、さんま、うなぎ |
また加工品を買う時は糖質や脂質、カロリーオフの食品を選ぶのがおすすめです。
内臓脂肪を減らす食事で、健康生活を始めよう!

内臓脂肪の蓄積は生活習慣病を始めとする様々な疾患の原因になり得るため、規則正しい食生活を意識して内臓脂肪のつきにくい生活を目指すことが大切です。この記事で紹介した内臓脂肪を減らす食事のコツを押さえて、健康的な食生活を実践してみましょう。
参考文献
厚生労働省 生活習慣病などの情報(e-ヘルスネット) 参照年月日:2025年7月25日
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/
国立大学法人 滋賀医科大学 調理による脂質量・エネルギー量の変化 参照年月日:2025年7月25日
https://www.shiga-med.ac.jp/~hqeiyo/fatty%20food.pdf
【監修者】
管理栄養士・和食ライフスタイリスト
合田 麻梨恵

大学卒業後、コンビニ商品開発を経て独立。2万件以上の予防医学に関する論文読破・発酵生産者100軒以上訪問・100名様以上の栄養指導経験を活かし、料理講師やセミナー講師、監修、書籍執筆などを行う。一般社団法人日本和食ライフスタイリスト協会代表理事、「中高年のための食と予防医学」の著者。