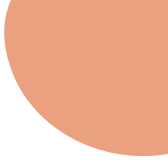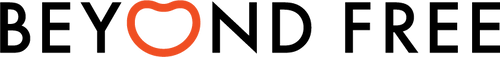【一覧】日本・世界の発酵食品と微生物の種類|効果的な食べ方など

発酵食品が健康に良いと聞いて、どのような食品があるのか、どのように食事に取り入れたら良いか気になっている方もいるのではないでしょうか?この記事では発酵食品とは何かについて解説し、発酵食品の種類や健康への良い影響、効果的な食べ方などを紹介します。ぜひ毎日の食事に役立ててください。
発酵食品とは

発酵食品とは、食品に含まれる有機物が発酵することで味わいや栄養、保存性などが高まった食品です。また発酵とはカビや菌、酵母などの微生物が食品に含まれるたんぱく質や糖類を分解した結果、ヒトにとって有益になる変化を言います。
世界最古の発酵食品は、紀元前5000年頃、牛乳から偶然にできたヨーグルトと考えられています。日本の記録に残っている最古の発酵食品は奈良時代のウリの塩漬けで、平安時代になると酒やしょうゆ、酢、味噌などの原型や野菜の酢漬けも登場したそうです。
日本の発酵食品の一覧

和食には調味料や漬物、郷土料理やその他の多岐にわたる発酵食品が存在するため、日本は「発酵王国」と呼ばれています。ここでは日本を代表する発酵食品を種類別に見ていきましょう。
調味料
和食で使われる調味料のうち、醤油や味噌、酢、みりん、塩麹、醤油麹、酒粕、米麹甘酒などが該当し、多くは米や大豆を発酵させて作られます。ユニークなものとしては、魚を米麹と塩で発酵させて作る魚醤も発酵食品です。日本三大魚醤として、しょっつる(秋田)、いしる(能登)、いかなご醤油(香川)が知られています。
漬物
漬物には非発酵の種類もあれば、野菜などの食材を塩や麹、酒粕などの床に漬け込んで乳酸発酵させた種類もあります。代表的な発酵漬物には京都のしば漬け、奈良の奈良漬け、東北の三五八漬け(さごはちづけ)があり、各々の作り方は以下です。
【しば漬け】
きゅうりやなす、みょうがなどを赤しその葉と塩を交互に漬けて作られます。
【奈良漬け】
シロウリなどの野菜を塩漬けし、さらに酒粕に複数回漬け込んで作られます。
【三五八漬け】
まずは塩3:麹5:米8の割合で1ヶ月程度置き三五八の素を作ります。その後、きゅうりやなす、にんじん、かぶなどの野菜を三五八の素に1日程度漬けて完成です。
郷土料理
日本の郷土料理には発酵食品も多くみられ、少し珍しいところでは以下のような食品があります。
秋田県北部でお盆のお供え料理として伝わっている赤漬け(赤ずし、けいとまま)は、炊いたもち米に塩揉みした赤じそと酢、砂糖を混ぜて数日間寝かせたものです。きゅうりやみょうがを入れることもあり、赤じその赤紫が目にも美しく、爽やかな酸味があるため暑い夏でも食欲をそそります。
埼玉県秩父地方の常備菜おなめ(なめ味噌)は大豆をおなめこうじ(麦麹)で発酵させて作られる発酵食品です。お好みの野菜や漬物などを刻んで入れる場合もあります。
熊本県の郷土料理である豆腐の味噌漬けはクリームチーズのような味わいが特徴です。硬い木綿豆腐を水切りし、味噌に漬け込んで作られます。
その他
上述した調味料や漬物、郷土料理以外にも、和食には多種類の発酵食品があります。大豆を納豆菌で発酵させて作られる納豆、蒸し米を米麹と酵母で発酵させる日本酒は日本を代表する食品です。またカビ付けの工程を経て作られる鰹節(本枯節)、碁石茶などの発酵茶、小麦粉を乳酸発酵させて作られるくず餅なども発酵食品と言えます。
国別!世界の発酵食品の一覧

アジア、ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、中南米にも独自の発酵食品があります。ここでは、各地域の発酵食品を珍しいものを含めて紹介します。
アジア
インドネシアにはテンペという大豆発酵食品があり「インドネシアの納豆」と呼ばれることもあります。大豆をクモノスカビの一種であるテンペ菌で発酵させたもので、日本の納豆よりも臭いや粘り気は少なくクセがないため、日本や欧米のスーパーでも取り扱っている場合があります。
フィリピンのナタデココは、ココナッツ果汁に酢酸菌の一種であるナタ菌をまぜて発酵させた際に液体表面にできるゲル状の上澄みをダイス状にカットして作られます。独特の歯ごたえがあり、ヨーグルトやパフェなどのデザートの具材として人気です。
タイのナンプラーはカタクチイワシなどの小魚を塩漬けして発酵させた魚醤で、タイ料理に欠かせない調味料となっています。
ヨーロッパ
ドイツの肉料理の付け合わせとしてポピュラーなザワークラウトは、キャベツを千切りにして乳酸発酵させて作られる漬け物で、爽やかな酸味が特徴です。
イタリアのバルサミコ酢は、濃縮したブドウ果汁を酢酸菌で発酵させてから長期間、樽で熟成させて作られます。肉料理やパスタのソースとして、またデザートのトッピングとして用いられており、香り高く濃厚な甘酸っぱい味わいが特徴です。
イギリスのマーマイトは、ビール醸造の副産物である酵母に塩や野菜エキスを加えて発酵させた調味料で、主にパンに塗って食べられます。黒っぽい茶色のペースト状で塩辛く、独特の香りと苦みもあるため、人によって好みが分かれる食品です。
その他
オーストラリアにもイギリスのマーマイトとよく似た調味料のベジマイトがあり、酵母を主に麦芽エキスや塩を加えて発酵させた食品です。
エチオピアで主食として食べられているインジェラは、イネ科の穀物テフの実を製粉してから水を加えて乳酸発酵させて作られます。小麦や白米と同じイネ科の穀物が主原料のため甘みがありますが、発酵が進むにつれて酸味が強くなるのが特徴です。
アフリカや中南米が主な産地のカカオ豆から作られるチョコレートも発酵食品です。カカオ豆の発酵工程はたったの数日で、その間に酵母と乳酸菌、酢酸菌など複数の微生物が発生し、成分を変化させます。チョコレート特有の味や香り、食感はこの発酵過程で生まれます。
発酵食品に関わる微生物の一覧

発酵食品に関わる微生物にはカビ、酵母、細菌の3つがあります。
発酵に役立つ主なカビはコウジカビ(麹菌)、アオカビ、カツオブシカビなどです。麹菌は日本の国菌に指定されており、味噌や醤油、漬物、日本酒、焼酎、甘酒、米酢、みりんなどの醸造に用いられます。また培地とする食材によって米麹や麦麹、大豆麹などの違いがあります。
酵母は糖をアルコールと炭酸ガスに分解する働きをする微生物です。アルコールと炭酸ガスを生成することから酒の醸造に、炭酸ガスで食材を膨らませるためパン作りなどに用いられます。他にも、紅茶や塩辛、納豆、くさや、かつお節、味噌、醤油、漬物などの発酵過程にも酵母が関係しています。
細菌に該当するのは乳酸菌や酢酸菌、納豆菌などです。乳酸菌はチーズやヨーグルト、味噌、醤油、漬物などの発酵に関係します。また、酢酸菌は酢やナタデココの発酵、納豆菌は納豆の発酵を促す細菌です。
発酵食品を取り入れるメリット

食材を発酵させる微生物の種類にもよりますが、発酵食品には腸内環境を整える、免疫機能を高めるなど健康への良い効果が報告されています。
それらのメリットにつながるのはプロバイオティクスと呼ばれる生きた微生物です。乳酸菌や酢酸菌、納豆菌など発酵を起こす菌や、ヨーグルトや乳酸菌飲料などに含まれています。具体的には以下の記事も参考にしてください。
プロバイオティクスとは?菌の特徴や含まれている食品をご紹介
発酵食品の効果的な食べ方

健康的な食習慣として発酵食品を取り入れる際、効果を高める食べ方があります。主な2つを以下で紹介します。
プレバイオティクスと一緒に摂る
下部小腸や大腸まで届き、ヒトに有益な善玉菌の餌となりその増殖・活性化を助ける難消化性食品をプレバイオティクスと言います。2025年6月時点ではガラクトオリゴ糖やフラクトオリゴ糖、ラクチュロースなど、難消化性オリゴ糖に分類される物質です。
またプロバイオティクスとプレバイオティクスを一緒に摂る方法をシンバイオティクスと言います。それぞれの健康効果がさらに高まると言われているので、発酵食品を食べる時は組み合わせを意識して食べるように心がけてみてください。
発酵食品を食べ過ぎないようにする
発酵食品に定められた摂取量はありませんが、食べ過ぎるとデメリットもあります。発酵食品の種類によりますが、食べ過ぎるとカロリーや塩分を摂り過ぎてしまったり、腸内環境のバランスが崩れてしまったりする可能性があるので、適度な量を摂取するように心がけましょう。
気になった発酵食品から、取り入れよう!

カビや酵母、菌などの働きで食材が有益に変化した発酵食品には、調味料や漬物、酒、納豆や鰹節、郷土料理など多くの種類があります。発酵食品の適量摂取で健康に良い効果が期待できるとの報告もあるので、気になる発酵食品から毎日の食事に気軽に取り入れてみてください。難消化性オリゴ糖と組み合わせて摂るとさらに効果的です。
参考文献
公式サイト 農林水産省 参照年月日:2025年6月21日
https://www.maff.go.jp/index.html
熱帯農業研究15 (2): 114-115, 2022│熱帯農業研究15 (2): 114-115, 2022 大西章博 参照年月日:2025年6月21日
https://www.jstage.jst.go.jp/article/nettai/15/2/15_114/_pdf
公式サイト 独立行政法人 農畜産業振興機構 参照年月日:2025年6月21日
https://lin.alic.go.jp/alic/month/dome/2004/aug/wadai1.htm
プロバイオティクス/プレバイオティクスとは 日本プロバイオティクス学会 2025年6月21日
https://probiotics-org.jp/probiotics/