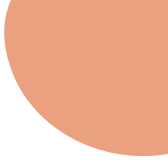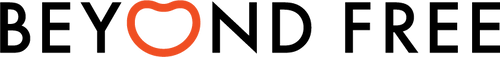五大栄養素の3つの働きとは?6大・7大栄養素もある?

ヒトの生命活動に重要な5つの栄養素を五大栄養素と呼びますが、その他に6大栄養素や7大栄養素と言う考え方もあることをご存じでしょうか?
この記事では五大栄養素の働きについて一つずつ解説し、第6・第7の栄養素の特徴も紹介しています。体に必要な栄養素とその役割を知ってバランスの良い食生活を目指しましょう。
五大栄養素の3つの働きとは

私たちは外界から食物を体内に取り入れて生命活動を維持していますが、生命活動の源になるのが栄養素です。栄養素は、そのはたらきによって三色食品群と呼ばれる以下のような3つのグループに分類されます。
-
体をつくる:たんぱく質、カルシウム
-
エネルギーになる:糖質、脂質
-
体の調子を整える:カロテン、ビタミンC
五大栄養素と言う言葉を聞いたことがある方もいると思いますが、五大栄養素とは炭水化物、脂質、たんぱく質、無機質(ミネラル)、ビタミンの5つを意味します。三色食品群でグループ分けした時に、これらの栄養素がどのような役割を持っているのか見ていきましょう。
体をつくる栄養素
体をつくる栄養素に分類されるのは、たんぱく質と無機質(ミネラル)、脂質で、それらを含有する食品は肉や魚、牛乳・乳製品、卵、大豆、海藻、小魚などです。
たんぱく質は筋肉を始めとして髪や爪など体のすべての構造をつくる材料になります。ここに分類されるミネラルの役割は、骨や歯などの構成成分です。脂質は細胞膜をつくる成分として必要になります。
エネルギー(カロリー)源になる栄養素
エネルギーのものになる栄養素は、炭水化物、たんぱく質、脂質です。これらは体を動かすためのエネルギー源になることから「エネルギー産生栄養素」と呼ばれています。以前は三大栄養素と呼ばれていたこともありました。これらを含む食品は米やパン、めん類、いも、油脂類です。
体の調子を整える栄養素
体の調子を整える働きがある栄養素はビタミンと無機質(ミネラル)で、含有食品は緑黄色野菜や淡色野菜、果物、きのこ類などです。
ビタミンには、食べ物から取り入れたたんぱく質、脂質、炭水化物が消化吸収され、体内でエネルギーとして利用されるのを助ける役割があります。ここに該当するミネラルの役割は生体機能の調整です。
各五大栄養素の働き

五大栄養素であるたんぱく質、脂質、炭水化物、ビタミン、無機質(ミネラル)の働きは、各々異なります。各栄養素の特徴や役割について詳しく解説します。
たんぱく質
たんぱく質は、細胞をつくっている主要な成分であり、筋肉や皮膚、髪、臓器などの材料です。また生命機能の維持に欠かせないホルモンや体内から異物を除去するための抗体、消化・吸収・代謝に必要な酵素の主要成分でもあります。構造を見るとたんぱく質は20種類のアミノ酸が約50~1,000個結び付いており、アミノ酸の配列や結合している数によって働きなどが異なります。
良質なたんぱく質食品とされるのは、たんぱく質の含有量が多く、体内における利用率が高い食品で、例えば肉類や卵、豆類などです。たんぱく質が不足する欠乏症になると、体力低下や免疫機能の低下、成長障害などを来す可能性があります。
以下の記事では良質なたんぱく質を含むと言われる大豆について、詳しく解説しています。
大豆のたんぱく質ってすごい?含有量や種類、大豆食品や野菜などとの比較
脂質
水に溶けない脂質は体内のエネルギー源になる他、細胞膜の主な構成成分です。脂質は大きく3つの種類に分かれ、次のように分類されます。
-
単純脂質:中性脂肪
-
複合脂質:リン脂質、リポたんぱく質
-
誘導脂質:脂肪酸、コレステロール、ステロイド
油脂の一種であるリノール酸やα-リポ酸は必須脂肪酸と呼ばれ、体内で合成できないため食べ物からの摂取が必要です。また脂質を摂り過ぎると使われずに余った分が中性脂肪として体内に蓄積されるため、肥満や生活習慣病につながる可能性があり、注意が必要です。
炭水化物
炭水化物は炭素と水素が結合した化合物です。炭水化物と言えばご飯やパンを思い浮かべる方が多いと思いますが、実は糖質と食物繊維の2つに分かれ、これらを総称して炭水化物と言います。
糖質
糖質は体内で消化されてエネルギーとして使われます。糖質にも種類があり、その分類は次の通りです。
-
単糖類:ブドウ糖、果糖、ガラクトース
-
少糖類(オリゴ糖)*:二糖類(ショ糖、麦芽糖、乳糖)、三糖類
-
多糖類:消化性多糖類(でんぷん、グリコーゲン)
*定義はやや曖昧のため二糖類を含める場合とそうでない場合がある
糖類はエネルギー源のため不足すると疲れやすくなったり集中力が低下したりします。特にブドウ糖は脳の主要なエネルギー源であり、不足によって意識障害が起こるケースもあります。
過剰な糖質は、脂質の場合と同様に中性脂肪の蓄積につながり、肥満や生活習慣病を招く原因になるでしょう。
食物繊維
食物繊維は食品中に含まれる、ヒトの消化酵素で消化できない物質を指します。水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2つに分かれ、便通を良くしたり、余分な脂質や糖質、ナトリウムを体外に排出したりする役割があります。
健康に有用な働きを持つことから、第6の栄養素と呼ばれることもある物質です。食物繊維について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。
ビタミン
ビタミンは体の生理機能を調整する働きがある有機化合物です。体内ではほとんどつくれない栄養素のため、食べ物からの摂取を必要とします。
ビタミンは大きく分けると、水に溶けやすい水溶性と油に溶けやすい脂溶性があります。水溶性ビタミンは必要量以上に摂っても尿として体外へ排出されるため過剰摂取になる心配はないと言われており、該当するのはビタミンB群とビタミンCです。
脂溶性ビタミンは肝臓や脂肪組織などに蓄積されています。水溶性ビタミンのように尿中へ排出されないため、摂りすぎによる過剰症に注意が必要です。ビタミンAとビタミンD、ビタミンE、ビタミンKが該当します。
無機質(ミネラル)
ミネラルは無機質とも呼ばれ、体を構成している4元素(酸素、炭素、水素、窒素)以外のものを指します。ミネラルもビタミンと同様に体内でつくれないため、食べ物から摂取しなければなりません。
またミネラルには相互作用があり、単体だけを摂取するのではなく、バランス良く摂ることも必要です。ミネラルは不足すると欠乏症による体の不調につながりますが、一方で摂りすぎると過剰症を引き起こす物質も存在します。ミネラルは次のように、多量ミネラルと微量ミネラルに分かれます。
-
多量ミネラル:カルシウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、リン
-
微量ミネラル:亜鉛、鉄、銅、ヨウ素、マンガン、セレン、モリブデン、クロム
7大栄養素が存在する?

厚生労働省で定義されているものではありませんが「フィトケミカル」を加えて7大栄養素とする考え方も存在します。フィトケミカルとは野菜や果物に含まれる化学物質を指し、健康への影響が注目されるものです。
フィトケミカルの例としては大豆のイソフラボンや、たまねぎのケルセチン、ブルーベリーのアントシアニンなどが挙げられます。
栄養素の働きを理解して、不足するものを補おう!

炭水化物、脂質、たんぱく質、無機質(ミネラル)、ビタミンの五大栄養素はその働きによって3つのグループに分けられ、それぞれ体の機能を維持するのに重要な役割を果たしています。さらに食物繊維は第6の栄養素、フィトケミカルは第7の栄養素として健康な体づくりを支えています。
各栄養素は働きが異なり、食事からすべての種類をバランス良く摂取することが大切です。栄養素ごとの特徴や働きを理解して、バランスの取れた食生活を心がけましょう。
参考文献
三色食品群と六つの基礎食品 佐世保市 参照年月日:2025年2月5日 https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/kenkou/hiroba/3syokubunrui6ttsunokisosyokuhin.html
実践食育ナビ 農林水産省 参照年月日:2025年2月5日 https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/zissen_navi/index.html
栄養に関する基礎知識 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 参照年月日:2025年2月5日
https://www.ncvc.go.jp/hospital/pub/knowledge/diet/diet01/
e-ヘルスネット 厚生労働省 参照年月日:2025年2月5日
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary
脂質やトランス脂肪酸が健康に与える影響 農林水産省 参照年月日:2025年2月5日 https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trans_fat/t_eikyou/
ファイトケミカル・食物繊維の健康増進機能~抗炎症作用~Health Promotion Function of Phytochemicals and Dietary Fiber: Anti-Inflammatory Function 江頭祐嘉合 千葉大学大学院園芸学研究科 教授 博士(農学) 参照年月日:2025年2月5日
https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/105016/S18808824-72-P002.pdf