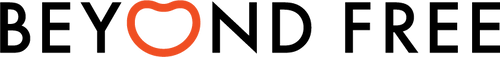きのこに含まれる栄養とその働きとは|おいしさと栄養を逃さない調理法も
「きのこってヘルシーと言われるけど、実際にどんな栄養があるの?」そう思っていませんか?
この記事では、きのこが持つ栄養と私たちの体にどう働くのかを解説し、さらにきのこのおいしさと栄養を最大限に引き出す調理法も紹介します。家族の健康のために、食卓ではきのこを上手に活用しましょう。
きのこに栄養はない?種類別に比較!

きのこは低カロリーですが、栄養がないわけではありません。それどころか、5大栄養素に分類されているビタミン・ミネラルを豊富に含んでいます。ここでは代表的な9種類のきのこの栄養素を、成分表を見ながら比較してみましょう。
|
|
食物繊維総量(g) |
カリウム(mg) |
ビタミンB1(mg) |
ビタミンB2(mg) |
ビタミンD(μg) |
|
えのきたけ |
3.9 | 340 | 0.24 | 0.17 | 0.9 |
|
ぶなしめじ |
3.5 | 370 | 0.15 | 0.17 | 0.5 |
|
ほんしめじ |
1.9 | 310 | 0.07 | 0.28 | 0.6 |
|
なめこ/株採り |
3.4 | 240 | 0.07 | 0.12 | 0 |
|
エリンギ |
3.4 | 340 | 0.11 | 0.22 | 1.2 |
|
ひらたけ |
2.6 | 340 | 0.40 | 0.40 | 0.3 |
|
まいたけ |
3.5 | 230 | 0.09 | 0.19 | 4.9 |
|
マッシュルーム |
2.0 | 350 | 0.06 | 0.29 | 0.3 |
|
生しいたけ/菌床栽培 |
4.6 | 290 | 0.13 | 0.21 | 0.3 |
※すべて生、100gあたりの量
※出典:文部科学省|日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
きのこに含まれる食物繊維量を高い順に見ていくと、えのきたけ や ぶなしめじ、まいたけなどが挙げられ、まいたけはビタミンDも多いです。きのこ類に含まれる具体的な栄養素や働きについては以下で詳しく紹介します。
食物繊維
食物繊維はヒトの消化酵素では分解されない成分で「第六の栄養素」とも呼ばれています。便秘を解消し腸内環境を整え、免疫機能の向上や生活習慣病の予防にも寄与します。きのこ類は低カロリーながら食物繊維が多く、毎日の食事に積極的に取り入れたい食材です。
食物繊維について詳しく知りたい方、食物繊維の多い食べ物などを知りたい方は以下の記事も参考にしてください。
食物繊維の水溶性と不溶性の違いとは?食品に含まれる割合の一覧も
食物繊維の多い食べ物の項目別ランキング!摂取するコツもご紹介
β-グルカン
β-グルカンはきのこ、特にしいたけに多く含まれる多糖類の一種で、きのこの種類によって含有量が異なります。免疫機能の維持や向上に関連すると言われている栄養成分です。
カリウム
カリウムは、体内の水分バランスや血圧の調整に重要な役割を果たすミネラルです。ナトリウム(塩分)を体外に排出し、高血圧の予防にも役立ちます。また、筋肉の収縮や神経の伝達にも関与しており、健康な心臓や筋肉の働きを支えるためにも欠かせません。
ビタミンB1
ビタミンB1は、糖質やたんぱく質をエネルギーに変換する際に不可欠な栄養素です。
不足すると、疲労感やだるさを感じやすくなる他、手足のしびれやむくみと言った神経や循環に関わる不調が現れる可能性もあります。さらに長期的な欠乏は糖代謝の異常を招き、糖尿病のリスクを高めてしまうので注意が必要です。
ビタミンB2
ビタミンB2は、糖質・脂質・たんぱく質の代謝を助け、エネルギー産生に不可欠な栄養素です。皮膚や粘膜の健康維持に重要で、不足すると口内炎や肌荒れの原因にもなります。成長や細胞の再生にも関与し、体内の活性酸素を抑える働きがあるため健康的な体づくりに欠かせません。
ビタミンD
ビタミンDは、カルシウムやリンの吸収を助け、骨や歯を丈夫に保つために欠かせない栄養素です。筋力の維持や免疫機能の調整にも関与し、感染症や慢性疾患の予防にも役立つとされています。
日光を浴びることで体内でも合成されますが食品からも摂取でき、ビタミンD2はきのこ類に含まれているので意識して摂取しましょう。
きのこの旨み成分を種類別に比較!

きのこには「うま味成分」として知られるアミノ酸の一種であるグルタミン酸が豊富に含まれています。グルタミン酸は昆布だしにも含まれる成分で、大切な栄養分であるとともに味に深みを与える重要な役割を担います。
以下に、代表的な8種類のきのこに含まれるグルタミン酸の含有量を比較してみました。
・えのきたけ:260mg
・ぶなしめじ:320mg
・なめこ/株採り:190mg
・エリンギ:280mg
・ひらたけ:400mg
・まいたけ:220mg
・マッシュルーム:340mg
・しいたけ:450mg
※すべて生、100gあたりの量
※出典:文部科学省|日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
中でも、ひらたけ や しいたけは特にグルタミン酸の含有量が高く、料理に豊かな旨みを加えてくれます。
また、しいたけはグルタミン酸に加え「グアニル酸」と言うもう一つのうま味成分も含まれており、これらの相乗効果によってさらに強い旨みを生み出します。調理に取り入れることで自然な味わいを引き出せるのが特徴です。
おいしいきのこの選び方

きのこを選ぶ時は、かさが開ききっていない半開きのものを選びましょう。かさが閉じているものは成熟していないため栄養価が十分ではなく、反対にかさが開ききっているものは時間が経過しており痛みやすくなります。
また、かさの裏側が白いものは収穫直後で鮮度が高い証拠。さらに軸が太く弾力のあるものは、水分をしっかり含んでいて調理しても風味が損なわれにくく、食感も良好です。これらの特徴を意識して選べば、よりおいしくきのこを味わえるでしょう。
おいしく、栄養を逃さない調理法

きのこの栄養やうま味を最大限に活かすためにも、以下3点を意識して調理してください。
水洗いはしない
きのこを調理する際、水で洗うのは避けましょう。きのこに含まれる水溶性ビタミンやミネラルは水にさらすことで流出してしまい、せっかくの栄養が損なわれてしまいます。
また水洗いは、きのこ特有の風味が落ちる原因にもなります。汚れが気になる場合は乾いた布やキッチンペーパーで軽くふき取るか、ブラシを軽くあてて汚れを落とす程度にとどめるのが理想的です。
油を使うメリットも
きのこに含まれるビタミンDは、脂溶性ビタミンであり油と一緒に摂取することで体への吸収率が高まります。例えば、きのこのバター炒めやオリーブオイルを使ったソテーは栄養面でも理にかなった調理法です。
さらに、油を使うことでコクや香ばしさが加わり、料理の満足度もアップするでしょう。ただし油の使い過ぎはカロリーや脂質の過剰摂取につながるため、最小限に抑えるよう気を付けてください。
強火でサッと調理する
きのこの食感や香りを損なわないためには、強火で手早く調理するのもポイントです。長時間火にかけると水分が出てしまい、ベチャっとした食感になりやすいため炒める際はできるだけ短時間で仕上げるようにしましょう。
さらに、表面に少し焦げ目をつけることで香ばしさが増し、うま味も引き立ちます。シンプルな調理でも、火加減と調理時間を意識して きのこをおいしくいただきましょう。
おいしいきのこの食べ方

きのこは幅広い料理に使える万能食材で、日々の食卓に手軽に取り入れられます。例えば「きのこのバター醤油炒め」は数種類のきのこをバターと醤油でサッと炒めるだけで、香ばしく食欲をそそる一品に仕上がります。
また「きのこの炊き込みご飯」もおすすめ。だしの旨みを吸ったきのこがご飯に深い風味を与え、冷めてもおいしいのが魅力です。さらにヘルシー志向の方には「きのこたっぷりスープ」もぴったり。味噌やコンソメ、豆板醤などを合わせればメニューのバリエーションも増やせます。
きのこをより栄養価高く、摂取しよう!

低カロリーながら、栄養価を兼ね備えた食材である点がきのこのすごいところ。きのこの選び方、調理の仕方を少し意識するだけで、さらに価値を高めることが可能です。
しかもうま味成分がたっぷりと含まれているため、味わい豊かなメニューを楽しむことができます。ぜひこれらのポイントを参考に、積極的にきのこを取り入れてみてください。
参考文献
「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書 厚生労働省 参照年月日:2025年5月26日 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44138.html
生活習慣病などの情報(e-ヘルスネット) 厚生労働省 参照年月日:2025年5月26日 https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/
加齢に伴う免疫力低下とβ-グルカンの是非 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 参照年月日:2025年5月26日 https://www.ncgg.go.jp/hospital/iryokankei/letter/028.html
きのこは健康によい?多くのきのこに含まれる5つの栄養素、期待される効果なども解説 岩手県洋野町 ひろのポータルサイト 参照年月日:2025年5月26日 https://portal.town.hirono.iwate.jp/feature/feature-7610/