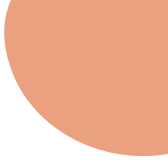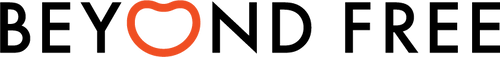乳酸菌が含まれる食品は?食物繊維と一緒に食べると良いって本当?

体に良い働きをするイメージがある乳酸菌は、様々な食べ物に含まれています。一般的に頭に浮かぶヨーグルトやチーズといった乳製品の他に、どのような食品に入っているのでしょうか?
本記事では乳酸菌が含まれる食品をご紹介するとともに、どのように摂取すると良いかを解説します。乳酸菌と食物繊維の関係にも注目して、健康づくりに役立ててくださいね。
乳酸菌とは

乳酸菌とは乳糖やブドウ糖と言った糖類を分解し、乳酸を作り出す細菌の総称です。乳酸菌と言う名の特定の菌を指すわけではありません。ヨーグルト・チーズ・漬け物などの発酵食品づくりに欠かせない微生物で、昔から活用されてきました。
善玉菌に分類される乳酸菌は、ヒトの体内にも存在します。腸内には100兆個もの細菌があり、健康維持には乳酸菌をはじめとする善玉菌の割合を増やすことが大切です。乳酸菌を含む食品を上手に摂取して、健康バランスを保ちましょう。
乳酸菌は2種類あるの?

微生物である乳酸菌は、形の違いによって2種類に分けられます。細長い棒状の乳酸桿菌(にゅうさんかんきん)と丸い形状の乳酸球菌(にゅうさんきゅうきん)です。これは形状で分類したものであり、乳酸菌として登録されているものの数は35菌属300菌種以上に上ります。
乳酸菌の中には、特定保健用食品の有効成分として利用されているものもあります。乳酸桿菌のラクトバチルス・ガセリや乳酸球菌であるストレプトコッカス・サーモフィルスの特定菌株が一例です。
乳酸菌が含まれる食品

食事に取り入れたい乳酸菌は、身近な食品に含まれています。乳製品から調味料まで代表的なものを確認しましょう。
ヨーグルト
ヨーグルトは加熱殺菌した牛乳に乳酸菌を加えて作られます。乳酸菌が乳糖を分解することで乳酸が生成し、牛乳に含まれるたんぱく質のカゼインが固まってできるのがヨーグルトです。
乳酸菌によって爽やかな酸味が付与され、プリン状に固まるため好ましい食感を生み出します。ヨーグルトに広く使われる乳酸菌は、球菌のストレプトコッカス・サーモフィルス菌とブルガリア菌と呼ばれる桿菌のラクトバチルス・デルブリキィ亜種ブルガリクスの2種類です。他にもカゼイ菌やガセリ菌、アシドフィルス菌などが利用されています。
チーズ
世界各地で食べられているチーズも、牛乳に乳酸菌を加えて作られます。生成した乳酸が有害微生物の増殖を抑えるので、牛乳を保存する方法としてチーズが生まれました。乳酸には適度な酸味を出したり、チーズを固める作用をサポートしたりする働きもあります。
熟成しないチーズはフレッシュチーズと呼ばれ、カッテージやモッツァレラなどが有名です。熟成チーズにはゴーダやチェダーがあり、使用する乳酸菌の種類が風味に影響を与えます。熟成の有無に関わらず、どちらも乳酸菌が含まれる食品です。
サワークリーム
爽やかな風味を持つサワークリームは、乳製品であるクリームに乳酸菌を加えて発酵させたものです。ラクトコッカス・ラクチスやラクトコッカス・クレモリスなど主に乳酸を生成する乳酸菌が一般的に使われています。
サワークリームはトーストにそのまま乗せたりデザートに活用したりする他、カレーやスープのコクを出す時にも重宝するクリームです。殺菌したクリームを原料に発酵させたものが主流のため、発酵バターの材料として使われることもあります。
なれずし
塩漬けした魚とご飯を漬け込んだ「なれずし」も、乳酸菌を含む食品です。和歌山県・三重県・秋田県など各地で作り方が異なるものの、ご飯の糖を乳酸発酵させることで長期保存に役立ててきました。
ラクトバチルスやエンテロコッカス、ペディオコッカスなどの乳酸菌が「なれずし」の発酵を支えています。熟成期間の長い「ふなずし」の他、短期間で漬け上げる「生なれずし」も親しまれています。
発酵した漬け物
漬け物の中で、発酵したものには乳酸菌が含まれています。日本ではすぐき漬・しば漬・すんき・たくあん・ぬか漬などたくさんの種類があり、海外でもザワークラウトやキムチなどが有名です。
多くの漬け物では食塩とともに漬け込み、雑菌が繁殖しないよう重しをして乳酸菌と酵母による発酵を行います。以前に漬けた漬菜や種となる菌が入った液を加えて、乳酸発酵を進めるのが特徴です。
日本酒
米と麹と水を原料にアルコール発酵させて造る日本酒にも、乳酸菌が欠かせません。アルコール発酵に必要な酵母を大量に培養したものが酒母(しゅぼ)と呼ばれます。「酒の母」の文字通り、酒母づくりは日本酒の出来上がりを大きく左右する大切な工程です。
乳酸を加えずに乳酸菌を育てる生酛(きもと)・山廃(やまはい)造りでは、乳酸菌が重要な働きを果たしています。主に使われるのは、ロイコノストック・メセンテロイデスやラクトバチルス・サケイと言った乳酸菌です。
ワイン
ワインの工程のひとつであるマロラクティック発酵でも、乳酸菌が活躍しています。元々は自然に混入する野生乳酸菌により起こっていた発酵工程ですが、近年では風味を改良するために乳酸菌スターターを加えることも一般的になりました。
リンゴ酸を乳酸と炭酸ガスに分解することで、ワインの酸味を和らげてまろやかな風味を作り出すのが乳酸菌の働きです。ワインのマロラクティック発酵には、オエノコッカス・オエニやラクトバチルス・プランタルムと言った乳酸菌がよく利用されています。
味噌
お馴染みの調味料である味噌も、乳酸菌を含みます。味噌は大豆・米・麦などの穀物原料に麴菌を加え、大豆や食塩を混ぜて作られたものです。発酵熟成の過程で添加された酵母・乳酸菌は、味噌らしい風味づくりに重要な役割を果たします。
乳酸菌が産生した乳酸の働きは味噌の色調の冴えを良くし、舌に感じる塩辛い味を低減させることです。また、大豆などの原料のにおいを抑える効果も期待できます。味噌に使われる乳酸菌は、エンテロコッカスやペディオコッカスと言う耐塩性のものが主流です。
醤油
醤油の製造工程でも、乳酸菌の働きが欠かせません。本醸造方式の場合、蒸した大豆と炒った小麦を混ぜたものに、種麹を加えます。出来た麹と食塩水を合わせた諸味を発酵熟成するタイミングで活躍するのが、乳酸菌です。
乳酸菌は麹菌や酵母とともに、醤油らしい風味の醸成に役立ちます。色や香りの良い醤油を造るには、乳酸菌が乳酸を適度に産生することが大切です。耐塩性のテトラジェノコッカス ・ハロフィルスは醤油乳酸菌と呼ばれています。
乳酸菌と食物繊維を一緒に食べるとどうなるのか

乳酸菌と食物繊維を一緒に摂ることで、腸内の善玉菌の割合を増やすことにつながります。ヒトの腸内には100兆個もの細菌が存在し、その種類は体に良い働きをする善玉菌、反対に良くない働きを及ぼす悪玉菌、どちらでもない中間の菌の3つです。健康維持のためには、善玉菌の占める割合を増やしましょう。
善玉菌である乳酸菌とあわせて、善玉菌のエサとなる「プレバイオティクス」を摂るのがおすすめです。プレバイオティクスであるオリゴ糖や食物繊維は、大豆やごぼうなどに多く含まれています。市販のサプリメントなどでプレバイオティクスを摂る場合は、食べ過ぎるとお腹が緩くなることもあるので注意してください。
以下の記事ではプレバイオティクスや、よく似た名称のプロバイオティクスについて詳しく解説しています。
乳乳酸菌を含む食品を摂取するポイント

健康のためには、栄養バランスの整った食事が基本です。乳酸菌を含む食品を摂取する際も、全体的なバランスを意識しましょう。例えば加糖ヨーグルトを摂り過ぎると糖分や脂質の過剰摂取につながります。健康づくりのはずがかえって健康を損なわないよう注意が必要です。
乳酸菌と食中毒の関係

乳酸菌には、食中毒菌の増殖を抑える働きがある点も押さえておきましょう。善玉菌の占める割合が高く腸内環境のバランスが良好な場合、乳酸菌が産生する乳酸や他の善玉菌が作る酢酸などにより、腸内環境が酸性に保たれます。一般的な食中毒菌は酸性環境が苦手なため、腸内環境が健康な方は食中毒の感染を抑制できると言われています。
食品以外にも!乳酸菌が活躍する分野

健康づくりに役立つ乳酸菌は、食品以外の分野でも活躍中です。酪農分野では牧草やトウモロコシといった飼料の保存性の向上に寄与しています。保存飼料であるサイレージに乳酸菌を利用することで、牧草サイレージの酪農発酵やトウモロコシサイレージの二次発酵を抑制し自然発酵よりも嗜好性の向上、採食量の増加、真菌の増殖抑制につながったためです。
また医療分野では、乳酸菌由来の抗菌ペプチドを利用した天然抗菌剤の開発も研究されています。
乳酸菌が含まれる食品で健康生活を始めよう!

健康生活を目指すなら、乳酸菌が含まれる食品を食事に取り入れましょう。あわせて食物繊維やオリゴ糖といったプレバイオティクスも摂取すれば、善玉菌の割合を増やすことにつながります。乳酸菌は身近な食品にも含まれているので、毎日摂取するように心がけてみてください。
以下の記事では腸活について詳しく解説しているので、健康づくりに役立ててくださいね。
参考文献
乳酸菌 e-ヘルスネット 厚生労働省 参照年月日:2024年8月8日 https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-026.html
腸内細菌と健康 e-ヘルスネット 厚生労働省 参照年月日:2024年8月8日 https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-05-003.html
乳酸菌の基礎知識 一般社団法人 全国発酵乳乳酸菌飲料協会 発酵乳乳酸菌飲料公正取引協議会 参照年月日:2024年8月8日 https://www.nyusankin.or.jp/lactic/basics
平山 洋佑、遠藤 明仁 腸内細菌学雑誌2016年30巻1号p.17-28 乳酸菌分類の現在とビフィズス菌・乳酸菌分類小委員会が提言した新規乳酸菌種提唱のための最少基準 参照年月日:2024年8月8日 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jim/30/1/30_17/_pdf
特定保健用食品について 消費者庁 参照年月日:2024年8月8日 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_specified_health_uses/
特定保健用食品許可(承認)品目一覧[Excel:231KB](令和6年8月6日更新) 消費者庁 参照年月日:2024年8月8日 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_specified_health_uses/
森地 敏樹 日本調理科学会誌2008年41巻1号p.55-60 食品における乳酸菌の利用とその働き 参照年月日:2024年8月8日 https://www.jstage.jst.go.jp/article/cookeryscience1995/41/1/41_55/_pdf/-char/ja
ビフィズス菌のヨーグルトはどのように作るのですか? よくある質問 公益財団法人 腸内細菌学会 参照年月日:2024年8月8日
https://bifidus-fund.jp/FAQ/FAQ_14.shtml
牛乳に酢や果汁を入れると一部が固まるのはなぜですか? 乳と乳製品のQ&A 一般社団法人 日本乳業協会 参照年月日:2024年8月8日 https://nyukyou.jp/dairyqa/2107_050_285/
ヨーグルトはどのように作るのですか? 乳と乳製品のQ&A 一般社団法人 日本乳業協会 参照年月日:2024年8月8日 https://nyukyou.jp/dairyqa/2107_042_491/
藤原 翠、荻原 博和 伝統的発酵ずしの微生物分布とその乳酸菌叢 日本食生活学会誌2022年33巻2号p. 99-105 参照年月日:2024年8月8日 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jisdh/33/2/33_99/_pdf
10-2 すしの始まりは“なれずし”から 公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構 米ネット 参照年月日:2024年8月8日 https://www.komenet.jp/bunkatorekishi/bunkatorekishi10/bunkatorekishi10_2
ふなずし 滋賀県 うちの郷土料理 農林水産省 参照年月日:2024年8月8日 https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/funa_zushi_shiga.html
宮尾 茂雄 発酵漬物における乳酸菌のはたらき 日本醸造協会誌2017年112巻6号p. 386-396 参照年月日:2024年8月8日 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan/112/6/112_386/_pdf/-char/ja
清酒と乳酸菌 あいち産業科学技術総合センターニュース2015年7月号No.160 あいち産業科学技術総合センター 参照年月日:2024年8月8日 https://www.aichi-inst.jp/other/up_docs/no160_02.pdf
恩田 匠 国産赤ワイン製造における市販乳酸菌スターターを用いたマロラクティック発酵試験 日本醸造協会誌2015年110巻9号p. 628-635 参照年月日:2024年8月8日
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan/110/9/110_628/_pdf
柳田藤寿 乳酸菌によるマロラクティック発酵(1) 日本ブドウ・ワイン学会誌VOLUME 5(1994) 参照年月日:2024年8月8日
https://asevjpn.jp/web/wp-content/uploads/2022/06/vol05_-no3_04.pdf
小泉 幸道、羽鳥 久志、柳田 藤治、伊藤 明徳、山口 元之 味噌熟成中の酵母と乳酸菌に関する研究 日本釀造協會雜誌1981年76巻3号p. 206-210 参照年月日:2024年8月8日 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan1915/76/3/76_3_206/_pdf
今井 学 味噌への乳酸菌利用 日本醸造協会誌1990年85巻9号p. 617-622 参照年月日:2024年8月8日 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan1988/85/9/85_9_617/_pdf/-char/ja
北川 学 発酵調味料“味噌”を知る 生物工学会誌 – 97巻4号 参照年月日:2024年8月8日
https://www.sbj.or.jp/wp-content/uploads/file/sbj/9704/9704_yomoyama.pdf
田中 昭光 醤油醸造での醤油乳酸菌の働きとその影響 生物工学会誌/日本生物工学会編90(6)p320-323,2012 参照年月日:2024年8月8日 https://www.sbj.or.jp/wp-content/uploads/file/sbj/9006/9006_tokushu-2_4.pdf
しょうゆの製造法 農林水産省 参照年月日:2024年8月8日 https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/c_propanol/soysauce.html
平野 勝紹 なるほど!?プレバイオティクス 生物工学会誌 – 95巻12号 参照年月日:2024年8月8日
https://www.sbj.or.jp/wp-content/uploads/file/sbj/9512/9512_biomedia_4.pdf
本間 満 酪農分野で活躍する乳酸菌 日本乳酸菌学会誌2017年28巻1号p. 18 参照年月日:2024年8月8日 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jslab/28/1/28_18/_pdf/-char/ja
永利 浩平、園元 謙二、善藤 威史、手島 大輔 乳酸菌由来抗菌ペプチドを利用した天然抗菌剤の技術開発飲み込んでも安全な天然抗菌剤とは? Kagaku to Seibutsu 58(1): 34-39 (2020) 参照年月日:2024年8月8日 https://katosei.jsbba.or.jp/view_html.php?aid=1246