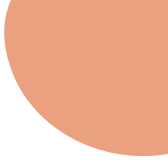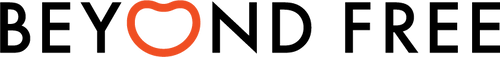一汁三菜の読み方と意味は?毎日の献立に悩まないコツや正しい置き方などもご紹介

「一汁三菜」という言葉を見かけたことはあっても「読み方が分からない」「どういう意味なのかよく知らない」という方もいるのではないでしょうか?
この記事では一汁三菜の考え方や献立の作り方、一汁三菜を取り入れるメリットについて、具体的な献立例を挙げながら紹介します。ぜひ毎日の食生活にお役立てください。
一汁三菜の読み方と意味とは

一汁三菜の読み方は「いちじゅうさんさい」です。「いちじるさんさい」と間違えやすいので注意してください。一汁三菜とはご飯やパン、麺類などの主食にみそ汁やスープなどの汁物1品とおかず3品(主菜1品+副菜2品)を合わせた献立を意味します。一汁三菜は栄養バランスの取れた献立を考える時に役立つ基準の1つです。
基本の三菜の考え方とは

メインのおかずである主菜には肉や魚、卵、大豆製品などを使った料理があり、主にたんぱく質を摂取できます。一方、副菜には野菜類(緑黄色野菜、淡色野菜)やきのこ類、海藻類、いも類などを使った料理があり、主にビタミン・無機質(ミネラル)・食物繊維を摂取できるように取り入れるサブのおかずです。
五大栄養素(炭水化物・脂質・たんぱく質・ビタミン・ミネラル)をバランスよく摂取できることが一汁三菜のメリットと言えます。献立を考える時は、先に主菜を決めると副菜を考えやすくなります。また、より簡単に栄養バランスが取れる考え方として「まごわやさしい」も有名です。
毎日の献立に悩まない!三菜の組み合わせ方のコツ

三菜の組み合わせ方がイメージしにくく、よく分からないという方もいるかもしれませんね。以下で、肉や魚、大豆製品を各々使った主菜料理にどのような副菜を組み合わせるのが良いかについて、コツと献立を紹介します。
主菜の種類から考える
まず、主菜の食材を選び、それに合わせて栄養バランスの取れる副菜を考えましょう。
牛肉や豚肉の主菜は肉豆腐やトンカツなど脂質・カロリーが高くなりがちなので、食物繊維を多く含む食材を副菜に取り入れてください。また、ほうれんそうのお浸しやわかめの酢の物など、油を使わない副菜も良いでしょう。
一方、鶏肉は牛肉や豚肉よりも低脂質・低カロリーの傾向があります。また、魚も比較的低カロリーなことに加えて、魚の油に含まれる必須脂肪酸のDHA・EPAに中性脂肪を下げる効果があると言われています。
その場合はミネラルも意識して、乳製品や野菜などを副菜に多めに取り入れるようにしましょう。例えば、鶏肉や白身魚と野菜(玉ねぎやキャベツ、パプリカ、ほうれんそう、にんじん、しめじなど)を一緒にスチームしてチーズフォンデュのように食べると、カルシウム(チーズ)や鉄分(ほうれんそう)、鉄分の吸収を助けるビタミンC(パプリカ、キャベツなど)も一緒に摂れるのでおすすめです。
ただし、鶏肉や魚を唐揚げやフライ、炒め物など油を使って調理すると脂質・カロリーが高くなりやすいため注意が必要です。
大豆製品の主菜は比較的低脂質・低カロリーですが、油や調味料を使いすぎないようにしてください。また、満足感を補うため少しボリュームを持たせるのがおすすめです。例えば主菜にボリュームを持たせる場合には野菜炒めや豆腐としめじの卵和え、副菜の場合に茶わん蒸し、ささみともやしのポン酢和えなども良いでしょう。
主菜の調理法から考える
主菜が揚げ物や炒め物など油を使う調理法では脂質とカロリーが高くなりやすいため、できるだけ油を使わず、食物繊維を多く含む副菜選びを意識してください。
主菜が焼き魚など焼き物の場合は主菜の食材が単品になりやすいので、副菜や汁物を必ず付けて主菜に足りない栄養素を補う必要があります。
また、サバのみそ煮や肉じゃがなどの煮物が主菜の場合は、食材に調味料が染み込みやすく塩分や糖分の摂取量が増えやすい点に注意が必要です。そのためカリウムや食物繊維の多い食材である緑黄色野菜や豆、根菜類を組み合わせた副菜を選びましょう。
一方、しゃぶしゃぶや肉と野菜の重ね蒸しなどゆで物・蒸し物の主菜は、肉類を食べすぎなければ脂質・カロリーを抑えられるので、副菜に卵や大豆製品などのたんぱく源や少々の油を使っても構いません。
一汁三菜を作るのが難しい日は

一汁三菜を作るのが難しい日は、ご飯とみそ汁だけにしても構いませんが、みそ汁にたんぱく源と野菜類・きのこ類・海藻類など複数の食材を使い、できるだけ栄養のバランスを摂るようにしましょう。
例えば、豚汁なら入れる具材の種類が多く、豚肉からたんぱく質、こんにゃく・大根・ごぼう・にんじん・青ねぎ・椎茸・わかめなどからビタミン・ミネラルも摂れます。または、豆腐と油揚げ、ねぎ、えのき、わかめなどを入れたみそ汁も良いですし、仕上げに豆乳を加えてコクとボリュームを出すことも可能です。
豚汁以外の選択肢として、たんぱく源・野菜類・きのこ類・海藻類を入れた野菜炒めとご飯の献立にしても良いでしょう。例えば、たんぱく源である豆腐・大豆ミート、野菜類であるにんじん・玉ねぎ・キャベツ、きのこ類である椎茸・えのき、海藻類である茎わかめ、薬味であるねぎ・しょうが・ニンニクなどを入れた野菜炒めなら、多種多様な栄養素も摂れて食べごたえのある主菜になります。
一汁三菜の形にこだわるのでなく、たんぱく源とビタミン・ミネラル・食物繊維を摂取できるように献立を考えることが大切です。その際は、いつもよりも1〜2種類、使う食材を増やす意識をしてみてくださいね。
一汁三菜を食べるメリット

一汁三菜を食べる主なメリットは次の3つです。
- 栄養バランスを整えやすい
- 発酵食品を取り入れる機会が増える
- 四季を楽しめる
それぞれについて以下で詳しく見ていきましょう。
栄養バランスを整えやすい
栄養バランスを厳密に整えるためには、日本食品標準成分表などを参照して算出する必要がありますが、健康体で、まず日々の習慣付けをする段階であればそこまで難しく考えなくても良いでしょう。その際役立つのが、一汁三菜の考え方です。一汁三菜をベースに汁物と主菜・副菜を揃えれば、ある程度の栄養バランスを整えることができます。
一汁三菜と言う和食の献立は低脂肪・低カロリーにしやすい点に加えて、食物繊維を摂取しやすい点などが長所です。特に、和食に特有の食材である大豆製品や海藻類を使った料理からは多くの食物繊維を摂取できます。
その反面、和食の献立はカルシウム不足や塩分過剰になりやすいです。その点は乳製品を使用してカルシウムを補ったり、塩分で味付けする代わりにだしや柑橘系、香辛料など、うま味や酸味、辛味など塩味以外を活用したりして調整する必要があります。
発酵食品を取り入れる機会が増える
みそや納豆、酢など、食事に発酵食品を手軽に取り入れる機会が多くなる点も、和食における一汁三菜の献立が持つメリットです。例えば一汁としてみそ汁を付けると、みそ(発酵食品)を摂取できますし、副菜として酢の物を付けると酢(発酵食品)を摂取できます。
発酵食品を取ると腸内に善玉菌を補充できるなど腸活にも繋がります。腸内環境が整うと免疫機能が向上するなど、健康増進の一つになるでしょう。
四季を楽しめる
旬の食材を使った料理を献立に取り入れる点も、和食の特徴の1つです。一汁三菜を意識すると、食を通して季節ごとの味わいを楽しむ機会も増えるでしょう。また自然の食材は旬が最もおいしくなる時期であり、旬以外の時期と比較して栄養含有量も高くなると言われています。
例えば、春が旬の食材の代表は菜の花やたけのこです。夏にはきゅうりやトマトなどの夏野菜が旬を迎えます。秋はさんまやさつまいも、冬は白菜や大根が旬です。意識して取り入れてみてはいかがでしょうか?
一汁三菜の正しい置き方

和食の器には並べ方のルールが定められており、一般的には食卓に向かって左側の手前にご飯、左側の奥にメインの副菜、右側の手前に汁物、右側の奥に主菜と言う配置になっています。漬物やお浸しなどサブの副菜はそれらの真ん中に置きます。また、魚の皿は頭を左に、腹を手前に置くことがルールです。頭の付いていない魚の切り身は皮を奥側に、幅の広い方を左にします。
ただし、関西や中国地方などではみそ汁を左奥に置く習慣もあり、歴史や文化背景によって配膳のルールもさまざまです。
生活に合った形で一汁三菜を取り入れよう!

一汁三菜を意識すると栄養バランスを整えやすくなりますが、たんぱく質・ビタミン・ミネラル・食物繊維を摂取できる料理を選べば主食とみそ汁だけ、または主食と主菜だけでも構いません。無理をせず、できるところから一汁三菜を取り入れると良いでしょう。
主菜を先に決めれば、足りない栄養を補える副菜を選びやすくなります。脂質やカロリーを抑えながら栄養を補給するには、植物性食品を活用するのも1つの選択肢です。BEYOND FREEではおからこんにゃくや大豆ミートを使った主食やおかずを取りそろえています。ぜひ、健康的な献立作りにお役立てください。
参考文献
日本の食事のよさって何かな? 農林水産省 参照年月日:2024年10月12日 https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_junior/pdf/02syoku_ryou.pdf
栄養素と食事バランスガイドとの関係 農林水産省 参照年月日:2024年10月12日 https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/zissen_navi/balance/guide.html
食事:魚がカラダによい理由 国立健康・栄養研究所 参照年月日:2024年10月12日 https://www.nibiohn.go.jp/eiken/question/
e-ヘルスネット 厚生労働省 参照年月日:2024年10月12日
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/
食べ物と日本の四季のつながりを見てみよう 農林水産省 参照年月日:2024年10月12日 https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomo_navi/learn/seasons1.html
ご存じですか?“和の配膳” 農林水産省 参照年月日:2024年10月12日 https://www.maff.go.jp/chushi/syokuiku/katudou/attach/pdf/26_jireishuu-23.pdf
味噌汁の配膳 東西で違い 商人気質 ルール変える(もっと関西) 日本経済新聞 参照年月日:2024年10月12日 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35014150V00C18A9AA2P00/
【監修者】
管理栄養士・和食ライフスタイリスト
合田 麻梨恵

一般社団法人日本和食ライフスタイリスト協会代表理事。大学卒業後、コンビニ商品開発を経て独立。2万件以上の予防医学に関する論文読破・発酵生産者100軒以上訪問・100名様以上の栄養指導経験から”令和の和食TM”で未病のない身体づくりを推進中。著書「中高年のための食と予防医学」など書籍執筆、監修、講演、コラム執筆、メディア出演など。