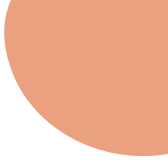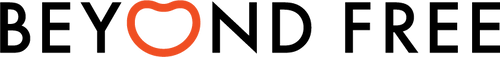納豆の栄養と効能!おすすめの食べ方など紹介

「納豆は健康に良い」と言う話を聞いたことがある方は多いと思いますが、具体的な効果効能についてはご存じない方も多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、納豆に含まれる具体的な栄養素やその効能について詳しく解説します。健康面を考慮したおすすめの納豆の食べ方についても紹介するので、ぜひ理想的な食生活の参考にしてください。
納豆は体に良いの?

納豆には植物性たんぱく質やカリウム・カルシウムなどのミネラル、ビタミンKなどの五大栄養素の他、ナットウキナーゼや大豆イソフラボンなどの健康機能成分も含まれています。
また納豆菌や食物繊維も含むため腸活にも活用される発酵食品です。腸活とは腸内に複数存在する多様な菌の中で、善玉菌を優勢にして腸内環境を整えることを指します。以上のことから、体に良い食品と言えるでしょう。
ただし納豆のみ食べていては摂取できる栄養素が偏ってしまうので、他の食品も併せて摂取するようにしてください。腸活については以下の記事でも紹介しています。
腸活に良い食べ物や組み合わせは?腸活をする理由も解説
納豆1パック(50g)の栄養素とその効能

納豆の具体的な栄養価や効能を知るために、以下の表に記載した2種類の納豆のエネルギーと主な栄養素を比較してみましょう。メーカーによって1パックあたりの納豆重量は異なりますが、ここでは1パック50gとして記載しています。
|
|
糸引き納豆 |
挽きわり納豆 |
|
エネルギー(kcal) |
92 | 93 |
|
たんぱく質(g) |
8.3 | 8.3 |
|
カリウム(mg) |
350 | 350 |
|
カルシウム(mg) |
46 | 30 |
|
マグネシウム(mg) |
50 | 44 |
|
鉄(mg) |
1.7 | 1.3 |
|
亜鉛(mg) |
1.0 | 0.7 |
|
ビタミンK(μg) |
440 | 470 |
|
食物繊維総量(g) |
3.4 | 3.0 |
※すべて50gあたりの量
※出典:文部科学省|日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
表を見て分かるように、種類が違えど納豆に含まれる栄養素に大きな差はなく、どちらも多様な栄養素をバランス良く含んでいます。ここからは、納豆に含まれる代表的な栄養素の働きについてそれぞれ詳しく解説します。
たんぱく質
私たちが生きていく上で欠かせない栄養素のひとつであるたんぱく質は骨や筋肉、皮膚や爪など人体のさまざまな組織を作る材料として使われます。この他、体の機能調整に必要な神経伝達物質やホルモンなどの生成をサポートする役割もあります。
大豆に含まれるたんぱく質については、以下の記事で詳しく解説しています。気になる方は、ぜひ合わせてご覧ください。
大豆のたんぱく質ってすごい?含有量や種類、大豆食品や野菜などとの比較
ミネラル(カリウム・カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛)
体の構成要素として知られるミネラルは複数の栄養素の総称です。納豆に含まれる各ミネラル成分について、詳しく見ていきましょう。
【カリウム】
食塩などに含まれるナトリウムを体外に排出させる作用を持つカリウムは、体内の塩分濃度を調整する上で重要です。この他、以下のような働きも期待できます。
・血液やリンパ液などの体液のpHバランスを整える
・筋肉の収縮を調整し体の動きをサポートする
・神経系に関わる
【カルシウム】
体内のミネラルの中で最も含有量が多いのがカルシウムで、主な役割は以下の通りです。
・骨や歯の形成をサポートする
・血液の凝固要因の働きを抑え、出血を予防する
・心筋の収縮作用を増やし、筋肉の興奮性を鎮める
【マグネシウム】
体内のさまざまな代謝の働きを助けてくれるマグネシウムは、以下のような役割を担っています。
・複数の体内酵素の働きを活性化させる
・神経情報の伝達や筋肉の収縮をサポートする
・体温・血圧を調整する
【鉄】
不足すると貧血をもたらすことで知られる鉄には、以下のような役割があります。
・酸素を全身に運ぶヘモグロビンの働きをサポートする
・機能鉄が不足した時に利用される貯蔵鉄として、肝臓や骨髄などに蓄えられる
【亜鉛】
全身の細胞に存在する亜鉛の主な役割は、以下の通りです。
・体内に侵入した細菌やウイルスに働きかけ、免疫機能を整える
・DNAやたんぱく質の生成をサポートする
・味覚機能を整える
納豆以外にもミネラルはさまざまな食品に含まれています。以下の記事では、ミネラルを含む食べ物に関して詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
ミネラルの多い食べ物の項目別ランキング!摂取するコツや働きもご紹介
ビタミンK
ビタミンKには血液を固める作用をサポートする働きがあります。この他、たんぱく質成分に働きかけ骨の形成を助けたり体内のめぐりを健やかに整えたりする作用も期待できます。
ビタミンKをはじめとしたビタミンを含む食べ物については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひこちらも参考にしてください。
ビタミンの多い食べ物の種類別ランキング!摂取するコツや働きもご紹介
食物繊維
適量摂取により便の量を増やす作用が期待できる食物繊維は、ヒトの体内にある消化酵素で消化できません。また不要な脂質や糖、ナトリウムなどを体外に排出させる働きをサポートする役割も担います。
食物繊維を多く含む食べ物や食物繊維のより具体的な効能については、以下の記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
食物繊維の多い食べ物の項目別ランキング!摂取するコツもご紹介
食物繊維の水溶性と不溶性の違いとは?食品に含まれる割合の一覧
ナットウキナーゼ
ナットウキナーゼは納豆のネバネバ部分に含まれており、たんぱく質を分解する働きがあるとされています。この他、血栓を溶かす作用があるとも言われ、体内のめぐりをサポートする成分としても知られている酵素です。
大豆イソフラボン
ポリフェノールの一種である大豆イソフラボンは、エストロゲンに似た作用を持つことで有名です。エストロゲンは月経の来るタイミングを調整したり思春期に起こる体的特徴を変えたりする重要な役割があります。
大豆サポニン
サポニンとは大豆などのマメ科の植物に多く含まれる渋味成分の一種で、抗酸化作用やコレステロール低下作用が期待できる成分として知られています。
レシチン
レシチンとは、大豆に限らず全ての生物の細胞に存在するリン脂質の一種です。リン脂質は体内の細胞膜を構成する重要な成分で、体内にある脂肪を貯蔵したりエネルギーとして活用したりする際に役立ちます。
ポリアミン
ポリアミンは体内にもともと存在する成分の一つで、年齢とともに徐々に減少していくことで知られています。細胞を増やしたり核酸をサポートしたり、核となる働きがある生理活性物質の一つです。
健康面から見たおすすめの食べ方

納豆はパックを開けたらすぐに食べられる便利な食品なので「調理せずにそのまま食べている」と言う方も多くいるでしょう。納豆に含まれるナットウキナーゼやビタミンB群などは加熱調理すると熱変化する可能性が報告されているので、生食は健康面から見ても良い食べ方だったのです。
しかし熱に弱いからと言って納豆の栄養価が極端に下がるわけではありません。調理方法のバリエーションを広げると、飽きることなく日常的に納豆を摂取しやすくなるはずです。
例えば、卵、大葉、ネギ、納豆、めんつゆを混ぜ合わせたものをご飯の上にかけたら、シンプルな納豆ご飯よりも満足度の高い一品が手軽に完成します。また、炒めた豚肉とキムチに納豆を合わせ、ご飯や中華麺の上に乗せて食べれば、それだけで一食分の栄養価を高められるでしょう。
また酢と一緒に食べたら納豆菌が死ぬのではないかと言う質問もありますが、そこは心配ないので気にせずに食べてください。
納豆をおいしく、健康的に取り入れよう!

スーパーやコンビニなど身近な場所でも購入しやすい納豆は、私たちの健康を内側からサポートしてくれる非常に心強い食品です。腸活をしたい方や日々の食生活を見直したい方は、まずは手軽に取り入れられる納豆を日常的に摂るよう意識すると、理想の健康生活に近付けるかもしれません。
今回紹介した内容も参考にしながら、ぜひ自分に合った方法で納豆を日々の食生活に取り入れてみてはいかがでしょうか?
参考文献
健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~ 厚生労働省 参照年月日:2025年6月23日
https://kennet.mhlw.go.jp/home/
e-JIM『「統合医療」に係る 情報発信等推進事業』 厚生労働省 参照年月日:2025年6月23日
https://www.ejim.mhlw.go.jp/public/index.html
「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書 厚生労働省 参照年月日:2025年6月23日
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44138.html
大豆及び大豆イソフラボンに関するQ&A 厚生労働省 参照年月日:2025年6月23日
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/02/h0202-1a.html#q04
腸内細菌叢の代謝制御によるポリアミン産生技術を用いた機能性食品の開発 公益社団法人日本農芸化学会 参照年月日:2025年6月23日
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu/59/12/59_591109/_pdf