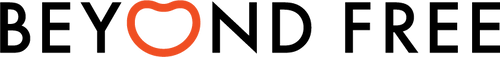健康的な食生活とは?健康寿命延伸のための食事のポイントを解説
「健康寿命」とは、不健康ではない状態での生活が期待できる平均期間を指す標です。健康寿命を延伸し充実した日々を過ごすためには、毎日の食生活を整えることが重要です。
しかし「具体的にどのような食事を摂ったら良いのか分からない」「健康的な食事の定義が難しい」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では健康的な食生活を送るためのポイントについて詳しく解説します。健康に配慮した食生活を送りたい方はぜひ参考にしてください。
健康的な食生活とは?

健康的な食生活と言うと抽象的で様々な解釈があるため、ここでは平成12年3月に当時の文部省・厚生省・農林水産省が共同策定し、平成28年6月に一部改正した「食生活指針」を参考にしていきます。
食生活指針とは国民一人ひとりの健康的な食生活を実現するため、バランスの良い食事を中心に食文化や食料資源の重要性など幅広く、生活の質(QOL)向上を重視した内容です。
以下は、食生活指針で掲げられている基本の10項目の引用です。
食事を楽しみましょう。
1日の食事のリズムから、健やかな生活リズムを。
適度な運動とバランスのよい食事で、適正体重の維持を。
主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
ごはんなどの穀類をしっかりと。
野菜・果物、牛乳・乳製品、豆類、魚なども組み合わせて。
食塩は控えめに、脂肪は質と量を考えて。
日本の食文化や地域の産物を活かし、郷土の味の継承を。
食料資源を大切に、無駄や廃棄の少ない食生活を。
「食」に関する理解を深め、食生活を見直してみましょう。文部省決定、厚生省決定、農林水産省決定
平成28年6月一部改正
「主食・主菜・副菜を基本とし、食事のバランスを整えよう」の項目では、一汁三菜の献立スタイルも該当します。一汁三菜の考え方については以下の記事で詳しく解説しています。
一汁三菜の読み方と意味は?毎日の献立に悩まないコツや正しい置き方などもご紹介
健康寿命延伸のための食事のポイント

食生活指針を参考にすると、健康的な食生活で大切なことは、食事の栄養バランスの他、運動や休養など、複数の要素があることが分かります。
ここからは、食事の栄養バランスについてより理解を深めていくため、6つの国立高度専門医療研究センターが掲げた「疾患横断的エビデンスに基づく健康寿命延伸のための提言(第一次)」の資料を基に、健康的な食生活を送るための8つのポイントについて詳しく解説します。
1.食塩の摂取を減らす
食塩の過剰摂取は健康を損なう直接的な要因となり得るため、世代を問わず、日々の食事では減塩を心がけることが大切です。厚生労働省が発表している「日本人の食事摂取基準 2025年版」によると、日本人の食塩摂取量の目標値は以下のように定められています。
-
成人男性:7.5g未満/日
-
成人女性:6.5g未満/日
しかし「令和5年 国民健康・栄養調査結果の概要」で発表された内容を見ると、以下に挙げる通り、男女ともに1日の平均食塩摂取量が目標値を上回っています。
-
20歳以上男性:10.7g/日(平均)
-
20歳以上女性:9.1g/日(平均)
減塩は高血圧などの生活習慣病のリスク低減にも影響するため、日々の食事では塩分濃度の高い食品摂取をできるだけ避けるようにしましょう。
2.野菜、果物を適切に摂取する
過去の複数の研究から野菜、果物の摂取が少ない群はそうでない群と比較して、がんのリスクが増加するという報告があり、健康に配慮した生活を送るには日々の食事で野菜、果物の適度な摂取が重要であると分かります。
食生活指針を具体的な行動に落とし込んだ「食事バランスガイド(厚生労働省と農林水産省の共同策定)」によると1日の理想的な野菜、果物の摂取量は以下の通りです。
-
野菜など副菜の目標摂取量:350〜420g/日
-
果物の目標摂取量:200g/日
しかし、近年では男女ともに双方の摂取量が目標値に届かないことが常態化しています。仕事や家庭の事情で食事準備にあまり時間をかけられない方は、まずは副菜をプラス一品するところから始めてみると良いでしょう。
野菜や食物繊維の摂取方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
食物繊維の水溶性と不溶性の違いとは?食品に含まれる割合の一覧も
3.大豆製品を多く摂取する
大豆製品や納豆や味噌などの発酵性大豆製品を多く摂ると、生活習慣病の発症リスクを低減させられるとの研究報告もいくつかあります。
日本人は古くから豆腐やおからなどの大豆製品を食べる習慣があるため、大豆製品の摂取量は国の推奨値からは大きく外れていないとされていますが、日々の食事では積極的に大豆製品を摂り入れるよう心がけることが大切です。
大豆や大豆製品に含まれるたんぱく質についてさらに理解を深めたい方は、ぜひ以下の記事も参考にしてください。
大豆のたんぱく質ってすごい?含有量や種類、大豆食品や野菜などとの比較
4.魚を多く摂取する
赤肉(牛肉や豚肉など)と比べ、良質なたんぱく質や多価不飽和脂肪酸を多く含む魚介類は、健康的な食生活を送る上で必要不可欠な食材です。魚介類に含まれるオメガ3脂肪酸の摂取が生活習慣病の発症リスクの低下につながると報告されています。
日本では魚介類を食べる習慣があるため、世界水準と比較すると魚介類由来のオメガ3脂肪酸摂取量の低さが死亡に与える影響は低い傾向にあるものの、近年では60歳以上の方よりも20〜59歳の方の魚介類摂取量の平均値は15g程度低いです。日々の食事で魚介類の摂取が不足しないよう注意しましょう。
5.赤肉・加工肉などの多量摂取を控える
赤肉や加工肉の多量摂取も生活習慣病の発症リスクを高めるとの研究報告があるため、日常の摂取量に気をつける必要があります。国際的な基準において赤肉・加工肉の摂取量は、以下のような目安が設けられています。
-
赤肉…1週間に500g未満
-
加工肉…できるだけ少なくする
たんぱく源の摂取には代替食や代替肉という選択肢もあるため、気になる方はぜひ以下の記事も参考にしてください。
いま代替食が選ばれる理由|今日から取り入れられる事例を紹介
代替肉とは?どんな種類や商品があるのかをご紹介
6.甘味飲料を控える
炭酸飲料や果実飲料など砂糖を多く含む甘味飲料の多量摂取も生活習慣病の発症リスクを高めると懸念されています。水分摂取時にはできるだけ甘味飲料を控え、水やお茶などの糖分を含まない飲料を選択するよう心がけましょう。
7.年齢に応じた脂質・たんぱく質・乳製品を摂取する
欧米人と比較して日本人の心筋梗塞の発症リスクが低いのは、魚介類や植物性たんぱく質から脂質を摂る習慣が関係していると言われています。そのためたんぱく源の種類もバランスよく取りながら、年齢を問わず脂質からのエネルギー摂取量は総エネルギー摂取量の20〜30%を目標量としましょう。
この他カルシウムを含む乳製品の摂取は、骨の健康に影響を与えるだけでなく、生活習慣病のリスク低下にも関わると言われています。日本人の一般的な食生活でカルシウムを過剰摂取することは考えにくいため、日々の食事では牛乳やヨーグルトなどの乳製品を一品追加することを検討してみましょう。
8.多様な食品を摂取する
私たちは日々、さまざまな食品を組み合わせて食事を摂取しています。食事にまつわる世界的な研究によると、以下2つの食事パターンは、生活習慣病の予防につながるという結果が報告されています。
-
DASH食
-
地中海食
DASH食とは高血圧予防・改善を目的とした食事療法で、主に以下のようなポイントに注意して食品を組み合わせます。
-
鶏肉以外の肉類を減らす
-
野菜や果物、低脂肪乳製品や全粒穀物、豆類、種実類などを十分に摂る
地中海食については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。
地中海食とは?特徴や健康効果とデメリットなど
健康的な食事で健康増進を!

健康寿命延伸のためには、健康的な食生活を送ることが必要不可欠です。今回紹介したように食品の摂取ポイントを押さえた食事を意識して効率的に食生活を整えていきましょう。
まずは副菜を一品足す、植物性食品を積極的に取るなどして無理のない方法で健康的な食生活を目指してみてはいかがでしょうか。
参考文献
e-ヘルスネット 厚生労働省 参照年月日:2025年2月4日
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/
食生活指針 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 参照年月日:2025年2月4日 https://www.nibiohn.go.jp/eiken/kouroukaken_health_economics/yougo_shokuseikatushishin.html
食生活指針 農林水産省 参照年月日:2025年2月4日 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000129379.pdf
疾患横断的エビデンスに基づく健康寿命延伸のための提言(第一次) 国立がん研究センター がん対策研究所 参照年月日:2025年2月4日
https://www.ncc.go.jp/jp/icc/cohort/040/010/6NC_20210820.pdf
~科学的根拠に基づく「健康に良い食事」について~ 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 参照年月日:2025年2月4日
https://www.nibiohn.go.jp/eiken/healthydiet/index.html#kenkojumyo
日本人の食事摂取基準(2025 年版) 厚生労働省 参照年月日:2025年2月4日
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44138.html
令和5年 国民健康・栄養調査結果の概要 厚生労働省 参照年月日:2025年2月4日
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001338334.pdf
健康日本21(第三次)について~栄養・食生活関連を中心に~ 厚生労働省 参照年月日:2025年2月4日
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001122156.pdf
【監修者】
管理栄養士・和食ライフスタイリスト
合田 麻梨恵

大学卒業後、コンビニ商品開発を経て独立。2万件以上の予防医学に関する論文読破・発酵生産者100軒以上訪問・100名様以上の栄養指導経験から”令和の和食TM”で未病のない身体づくりを推進中。著書「中高年のための食と予防医学」など書籍執筆、監修、講演、コラム執筆、メディア出演など。一般社団法人日本和食ライフスタイリスト協会の代表理事を務める。