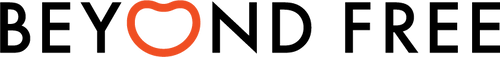海藻類の五大栄養素を比較!調理のコツと食べ方
健康的な食生活を心がけている方にとって、海藻は毎日の食事に積極的に取り入れたい食材のひとつではないでしょうか?
海藻は低カロリー・低脂質であるだけでなく、食物繊維やミネラル、ビタミンなど体にうれしい栄養素を含んでいます。この記事では海藻の種類や栄養素、おすすめの調理法や食べ方などを紹介するので、ぜひ参考にしてください。
海藻とは?定義や分類、海草との違い

海藻とは海中の主に岩礁域に生えている藻類で、代表的な種類は緑藻類・褐藻類・紅藻類などです。食用になる藻類には褐藻類を中心に約50種類があります。緑藻類ではスジアオノリ、褐藻類では わかめやヒジキ、もずく、マコンブ、紅藻類ではアサクサノリやテングサが食べられる海藻としてよく知られています。
海藻と似て非なるものが海草(うみくさ)です。海草は藻類ではなく花が咲いて種ができる種子植物で、根・茎・葉が区別されます。一方、海藻では根・茎・葉が区別されていません。また、海草は根や葉から栄養を吸収しますが、海藻の根は岩場などに固着するのみで栄養を吸収しない点などが異なります。
海藻類の五大栄養素を比較!どんな特徴がある?

海中で育つ藻類である海藻にはわかめやこんぶなど和食に欠かせない食材も含まれます。海藻と言うと低カロリーでヘルシーな印象を持つ方が多いと思いますが、実際にはどのような栄養が含まれているのでしょうか?
ここではよく食べられている海藻類11種類を取り上げ、エネルギー・食物繊維・カルシウム・鉄・ビタミンC・α-トコフェノール(ビタミンE)の含有量を見てみましょう。
|
順位 |
エネルギー(kcal) |
食物繊維(g) |
カルシウム(mg) |
鉄(mg) |
ビタミンC(mg) |
α-トコフェノール(mg) |
|
あおさ/素干し |
201 | 29.1 | 490 | 5.3 | 25 | 1.1 |
|
あおのり/素干し |
249 | 35.2 | 750 | 77.0 | 62 | 2.5 |
|
あまのり/ほしのり |
276 | 31.2 | 140 | 11.0 | 160 | 4.3 |
|
あらめ/蒸し干し |
184 | 48.0 | 790 | 3.5 | 0 | 0.6 |
|
うみぶどう/生 |
6 | 0.8 | 34 | 0.8 | Tr(微量) | 0.2 |
|
まこんぶ/素干し/乾 |
170 | 27.1 | 780 | 3.2 | 29 | 2.6 |
|
ひとえぐさ/素干し |
172 | 44.2 | 920 | 3.4 | 38 | 2.5 |
|
まつも/素干し |
252 | 28.5 | 920 | 11.0 | 5 | 13.0 |
|
もずく/塩蔵/塩抜き |
4 | 1.4 | 22 | 0.7 | 0 | 0.1 |
|
わかめ/乾燥わかめ/素干し |
172 | 29.0 | 830 | 5.8 | 19 | 1.2 |
|
ひじき/ほしひじき/ステンレス釜/乾 |
180 | 51.8 | 1,000 | 6.2 | 0 | 5.0 |
※すべて100gあたりの量
※出典:文部科学省|日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
このように、海藻類は全体的にカロリーが低い食材で低脂質です。最も低カロリーな海藻はもずく、最も食物繊維が豊富に含まれる海藻は乾燥わかめとなっています。また、カルシウムが多い海藻はひじきやひとえぐさ・まつも、鉄が多い海藻はあおのりです。ビタミンCはあおさ、α-トコフェノールはまつもに多く含まれています。
ビタミンやミネラルについては以下の記事で詳しく解説しています。
ビタミンの多い食べ物の種類別ランキング!摂取するコツや働きもご紹介
ミネラルの多い食べ物の項目別ランキング!摂取するコツや働きもご紹介
海藻ならではの食物繊維!フコイダン・アルギン酸とは
食物繊維は消化されずに大腸まで届く物質で、第6の栄養素とも呼ばれています。食物繊維の有用な効果は主に整腸、血糖値上昇抑制、血中コレステロール濃度低下などです。より詳しくは以下の記事を参考にしてください。
食物繊維の水溶性と不溶性の違いとは?食品に含まれる割合の一覧も
食物繊維の多い食べ物の項目別ランキング!摂取するコツもご紹介
海藻ならではの食物繊維にフコイダンやアルギン酸があり、その健康効果が注目されています。
フコイダンは わかめやもずくなど褐藻類だけに含まれる特有のヌメリ成分で、水溶性食物繊維の一種です。フコイダンには生活習慣病の予防をはじめ様々な生理作用があると言われています。
アルギン酸も褐藻類に含まれる水溶性食物繊維の一種です。海藻由来の低分子化アルギン酸ナトリウムはコレステロールの吸収を抑制する作用により「コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。」と特定保健用食品に認められています。
特定保健用食品とは消費者庁が定める基準です。人体の生理学的機能などに良い影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、摂取によって特定の保健目的が期待できると言った表示が許可されている食品を指します。
【海藻類別】特徴・下処理・保存方法・食べ方

栄養が摂れる海藻をもっと毎日の食事に活用するために、それぞれの特徴や下処理方法、保存方法、食べ方を知っておきましょう。ここでは、わかめ、ひじき、アカモク、もずくについて紹介します。
わかめ
褐藻類のわかめは葉、中芯/中助(くきわかめ)、胞子葉(めかぶ)の3部位に分かれており、わかめとして食べるのは葉の部分です。採ったばかりのわかめは褐色ですが、湯通しすると緑色になります。
<下処理・保存>
春先には生わかめが出回りますが、あまり日持ちしないため湯通ししてから冷凍保存がおすすめです。まず、大量の水で全体を洗ってから、火が通りにくい茎を葉から切り分けます。茎を20秒ほど茹でてから葉が緑色に変わるまでさっと湯通しし、氷水でしめます。
食べやすいサイズにカットしてからラップなどに包んで小分けし、保存袋に入れて空気を抜いて冷凍してください。味噌汁に入れる時は凍ったまま湯に入れて調理できます。酢の物やサラダなどに使う場合は約5分浸水解凍し、水気をしぼって使いましょう。
<食べ方>
湯通しした生わかめをしゃぶしゃぶの具として使うと食感を楽しめます。また、もやしやキャベツなどと一緒にナムルにする食べ方もおすすめです。
ひじき
ひじき製品には長ひじきと芽ひじきの2種類があり、同じ種類の海藻ですが使用する部分が異なります。歯ごたえのある長ひじきは長い茎の上部、柔らかい芽ひじきは小枝や芽の部分です。
<下処理・保存>
生ひじきは乾燥ひじきよりもふっくらとしていてみずみずしいところが魅力です。生ひじきは大量の水で洗って汚れを落としてから、大量のお湯で約3分、火が通るまで茹でます。粗熱が取れてから冷凍用保存袋に入れて冷凍庫で保存しましょう。
使う時は凍ったままで調理できます。煮物にしてから小分けして冷凍しておくと、献立を一品増やしたい時やお弁当などに手軽に使えて便利です。
<食べ方>
ひじきはスパゲッティの具材にしたり切り干し大根と一緒にサラダ風にしたりしてもおいしく食べられます。にんにくとの相性も良いので、にんにく風味で炒めてからサンドイッチの具材にする食べ方もおすすめです。
アカモク
京都府の丹後名産アカモクも海藻の一種で、健康増進が期待できる新素材としても全国各地で関心が高まっています。歯ごたえと粘りがアカモクの特徴です。わかめの芽かぶと食感が似ていますが、アカモクのほうがしっかりとした歯ごたえを楽しめます。
<下処理・保存>
生のアカモクには小さなゴミや泥が付着しているため、ボウルの水がきれいになるまで水を替えながら揉み洗いします。次に、先端から根元に向けて手でしごいて軸を取り除き、葉の部分を水洗いしてください。その後、大量のお湯で数秒~数十秒茹で、水で冷やしてから水切りし、冷凍保存用袋に入れて冷凍保存します。
<食べ方>
アカモクは茹でてから細かく刻んで食べるのが基本です。そばやうどんのトッピングにしたりポン酢やドレッシングと混ぜてサラダにトッピングする食べ方もあります。その他、餃子やオムレツ、スープなどの具材として加えるのもおすすめです。
もずく
独特のぬめりと柔らかさ、黒っぽい褐色の色が特徴の海藻であるもずくは、沖縄の食材としてよく知られています。もずくには多くの種類がありますが、食用とされているのは沖縄もずく(太もずく)ともずく(いともずく・ほそもずく)など6種類です。
<下処理・保存>
生のもずくは軽く水洗いするだけで食べられますが、日持ちしないことに注意が必要です。塩蔵もずくは内部まで塩分がしみこんでいるため、調理の前に塩抜きが必要です。十分に水洗いしてから塩が抜けるまで(約5分)水に浸して塩抜きを行います。
<食べ方>
スープの具材にもずくを活用できます。味付けは和風・中華風・韓国風などが合い、雑穀やトマト、卵、豆腐など他の具材と一緒に使うとバリエーションを出すことが可能です。他には、サラダの具材にもずくを加えてもおいしく食べられます。
昆布
昆布は種類が複数あり、採れる地域によって名称が異なります。昆布の90%以上は北海道産で、他には青森県や岩手県、宮城県などの三陸海岸沿いが主な産地です。
<下処理・保存>
切昆布など生食用の昆布は水洗いしてからカットして使います。乾燥昆布を保存する際は、使いやすい大きさにカットしてから密閉容器に入れ、戸棚の中など湿気の少ない場所で直射日光に当てずに保管してください。冷蔵庫や冷凍庫で保管することもできます。
<食べ方>
昆布を浅漬けやナムルに入れると旨み付けになります。また沖縄料理のクーブイリチー(昆布の炒め煮)のように油で炒めるとメインのおかずとして食べることが可能です。
栄養を逃さないための調理方法

ここでは、海藻に含まれるビタミンやミネラルを逃さず、効率的にとるための工夫について紹介します。
油を使って脂溶性ビタミンの吸収率を上げる
ビタミンAとビタミンKは脂溶性ビタミンです。脂溶性ビタミンは油との相性が良いため、油と一緒に食べることで吸収率を上げることができます。例えば、海藻サラダにごま油やドレッシングなどをかけて食べたり、油炒めにしたりすると良いでしょう。
ただし、油を使うことでカロリーが上がることには注意が必要です。いくら海藻が低カロリーな食材であっても調理法や調味料によってカロリーが高くなる場合があるため、食べすぎに注意してください。
ビタミンCと一緒に調理して植物性の鉄分の吸収率を上げる
植物性食材に含まれる鉄分はビタミンCと相性が良く、一緒に食べることで吸収率を高めます。逆に一緒に食べると吸収率が下がる組み合わせもあるので、一緒に食べないよう注意が必要です。詳しくは以下の記事を参考にしてください。
プラントベースで鉄の吸収率を高めるには?
調理を工夫して、海藻から栄養素を補給しよう!

海藻は低カロリー・低脂質であるだけでなく、食物繊維やカルシウム、鉄分、ビタミンC・Eも含む食材です。海藻の栄養を効率的に吸収するためには、調理や摂り方に一工夫すると良いでしょう。
参考文献
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 文部科学省 2025年5月28日
順応的管理による海辺の自然再生 国土交通省 参照年月日:2025年5月28日 https://www.mlit.go.jp/kowan/
生活習慣病などの情報e-ヘルスネット 厚生労働省 2025年5月28日 https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/
生活習慣病の予防と検査 女子栄養大学栄養科学研究所 2025年5月28日 https://llab.eiyo.ac.jp/ions/
特定保健用食品の許可表示例① 内閣府 2025年5月28日 https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/
特定保健用食品について 消費者庁 2025年5月28日 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/
食事中の脂質は脂溶性ビタミンの吸収を増加させる J-STAGE 2025年5月28日 https://www.jstage.jst.go.jp/article/vso/91/10/91_613/_pdf
医療・健康・健診・予防接種 船橋市 2025年5月28日 https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/iryou/012/p110604_d/fil/eiyou2.pdf