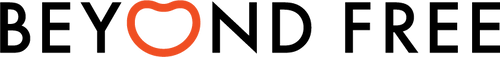野菜に含まれる栄養素とは?生・茹で・乾燥などで栄養価は変わる?
野菜は「何となく体に良いもの」と思っていても、具体的にどのような栄養素が含まれているのか知らない方もいるのではないでしょうか?この記事では野菜に含まれる栄養素や野菜を摂るメリットについて解説しています。
野菜の栄養を効率よく摂取するポイントに加えて時期や食べ方による栄養価の違いについても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
野菜に含まれている栄養素

野菜に多く含まれている栄養素はビタミン・ミネラル・食物繊維です。野菜は緑黄色野菜と淡色野菜の2つに大別され、緑黄色野菜にはβ-カロテン(ビタミンA)やカルシウムが多く含まれます。また淡色野菜にはビタミンCやカリウムが多く含まれるのが特徴です。
緑黄色野菜や食物繊維については以下の記事で詳しく解説しています。
食物繊維の水溶性と不溶性の違いとは?食品に含まれる割合の一覧も
野菜を摂るメリット

野菜は「栄養が多い食べ物」と言うイメージを多くの方が持っていると思いますが、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか?ここからは野菜を摂る3つのメリットについて解説します。
現代人が不足しがちな栄養素を補給できる
現代の日本人は、体に必要な栄養素が不足しがちだと言われています。各栄養素の必要摂取量を示した「日本人の食事摂取基準2020年版」の基準値と「令和5年国民健康・栄養調査結果の概要」で示された実際の平均摂取量を比較すると、年代にもよりますが前述したビタミンA、ビタミンC、カルシウムなどが不足していると言う結果でした。
さらに「健康日本21」において推奨されている野菜の摂取量が1日あたり350gなのに対して「令和5年国民健康・栄養調査結果の概要」で示された実際の摂取量が男女平均で256.0gです。つまり1日約100gの野菜が不足していると言え、これは約1品分の副菜に該当します。
以上から、日本人は野菜を多めに食べることで不足しがちな栄養素を補給できると言えるでしょう。現代人に不足している栄養素については以下の記事で詳しく解説しています。
新型栄養失調とは?症状や原因、対策を子供・高齢者などライフステージ別で紹介
機能性成分も摂取できる
野菜を摂ることは機能性成分の摂取にも繋がります。機能性成分とは生体調節機能を持つ食品成分です。生命活動に必須とされる栄養素ではありませんが、健康維持や有害物質から体を守るなど様々な機能的働きが期待できます。
カテキンやアントシアニン、イソフラボンに代表されるポリフェノールは機能性成分の一つです。他にもβ-カロテンに代表されるカロテノイドやだいこん・わさび・からしなどに含まれる辛味成分であるイソチオシアネートなどもあります。
機能性成分の働きや具体例については以下の記事で紹介しているので、ぜひご覧ください。
フィトケミカルとは何ですか?効果や含有する食品など
善玉菌のエサになり腸内環境を整えられる
野菜に含まれる食物繊維はヒトの消化酵素で消化されず、小腸で吸収されないまま大腸まで達します。食物繊維には便の体積を増やす役割だけでなく、プレバイオディクスとして腸内にいる善玉菌のエサになり腸内環境を整える働きなども知られています。
プレバイオティクスの詳細や腸活については以下の記事を参考にしてください。
プロバイオティクスとは?菌の特徴や含まれている食品をご紹介
腸活に良い食べ物や組み合わせは?腸活をする理由も解説
野菜を摂取するコツ

野菜は生のまま食べるよりも、調理した方が量を多く食べられたり食材によっては栄養素の吸収率を高められたりするメリットがあります。例えば120gの生野菜は両手に乗せると山盛りになるくらいの量ですが、加熱により片手に収まる程度の量までカサを減らせます。
野菜は加熱すると栄養素が失われると思われがちですが、β-カロテンなどは加熱によって栄養素の吸収率がアップする成分です。野菜の細胞はかたい細胞壁に覆われていて、そのまま食べても細胞壁に阻害され、栄養素が十分に吸収されません。
栄養素を吸収されやすい状態にするには野菜の細胞壁を壊す必要があります。調理のポイントは野菜を加熱したり細かく刻んだりする点です。加熱すると細胞壁がやわらかくなり、刻むと細胞壁が破壊されて食べた時に栄養素が吸収されやすくなります。
加熱調理に適している野菜の代表的なものは、トマトやにんじんです。脂溶性ビタミンであるβ-カロテンやビタミンD・E・Kは水に溶けにくく油に溶けやすいため、油で炒める料理にぴったりです。また加熱調理に強く、茹でたり煮たりする料理にも向いています。
またトマトジュースや野菜ジュースは野菜を加熱して細かく刻んで作られているので、リコピンやβ-カロテンなどの栄養素を効率良く体内に取り込める食品です。
よくあるQ&A

ここからは野菜に含まれる栄養について質問が多い内容を紹介します。よくあるQ&Aを参考にして野菜の栄養に関する疑問点を解消しましょう。
Q.旬の野菜は栄養価が高いって本当?
A.野菜の種類によりますが、季節で一部の栄養素の量が変わる野菜があります。例えば、ほうれんそうはビタミンCの含有量が収穫時期によって変動する野菜です。
下のグラフから分かるように、ほうれんそうの旬である冬期にはビタミンCの含有量が夏期の約3倍になります。

出典:独立行政法人 農畜産業振興機構|野菜をおいしく食べる
ほうれんそうは栽培技術や品種改良が進み、一年を通して食べられる野菜ですが、旬の冬に食べるとより多くの栄養を摂取できます。
Q.生・茹で・冷凍、どの野菜が栄養価高いの?
A.野菜や栄養素の種類によって違いはありますが、調理方法で栄養価が変わる場合があります。下のグラフは、ほうれんそうのカリウム量を調理別法に比較したものです。
※すべて100g当たりの量
※日本食品標準成分表(八訂)増補2023年を参考に作成
ほうれんそうのカリウム量については、生の状態での含有量が100g当たり690mgと高くなっています。次いでカリウム量が多いのは生のほうれんそうをゆでて調理したもので、100g当たり490mgです。それに比べて冷凍のほうれんそうはカリウム含有量が比較的低いと分かります。
続いて、ほうれんそうのβ-カロテン量についても下のグラフで調理法別に比較してみましょう。
※すべて100g当たりの量
※日本食品標準成分表(八訂)増補2023年を参考に作成
β-カロテンは冷凍のほうれんそうを油炒めにしたものが100g当たり7200μg、冷凍後に茹でたものが7100μgと高い含有量を示しています。一方で生のほうれんそうはβ-カロテンの含有量が100g当たり4200μgと、冷凍のほうれんそうに比べて少ないのが特徴です。
このように野菜の栄養素は生・茹で・冷凍で含有量が変化します。また冷凍ものでも、その後の調理方法が茹でるのか油で炒めるのかによって栄養素の量が変わります。
Q.乾燥野菜(干し野菜)の栄養価は高いの?
A.乾燥させた野菜は一般的に生野菜に比べて栄養価が高くなる傾向があります。下のグラフは、ぜんまいとだいこんを乾燥させたものと生の状態の栄養価を比較したものです。
|
成分 |
カリウム(mg) |
カルシウム(mg) |
β-カロテン(μg) |
ビタミンC(mg) |
|
生ぜんまい/若芽/生 |
340 | 10 | 500 | 24 |
|
干しぜんまい/干し若芽/乾 |
2200 | 150 | 680 | 0 |
|
だいこん/根/皮つき/生 |
230 | 24 | 0 | 12 |
|
切干しだいこん/乾 |
3500 | 500 | 2 | 28 |
※すべて100g当たりの量
※日本食品標準成分表(八訂)増補2023年を参考に作成
カリウム、カルシウムについては生の状態よりも乾燥野菜にした方が100g当たりの含有量が多くなっており、β-カロテン量についても差は小さいものの乾燥野菜の方が含有量が多くなっています。これは乾燥している間に野菜から水が抜け、栄養素が凝縮されるためです。
ただしビタミンC量については乾燥させた大根の含有量が多いのに対して、ぜんまいの場合は生の状態の方が多くなっています。ぜんまいを乾燥させた場合、ビタミンCは失われてゼロになるのが特徴です。
野菜から不足しがちな栄養素を摂取しよう!

野菜を始めとする植物性食品には様々な栄養素が含まれ、積極的に摂ることで体に良い働きが期待できます。現代の日本人は野菜の摂取量が不足しがちなため、野菜を使った副菜を1品増やすなどして1日の摂取目安量350gを目指しましょう。
この記事で紹介したように野菜の栄養価は時期や調理方法によって変わります。調理や食べ方を工夫して野菜の栄養素を効率良く吸収しましょう。
参考文献
e-ヘルスネット 厚生労働省 参照年月日:2024年12月25日 https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/
栄養成分別野菜ランキング 独立行政法人 農畜産業振興機構 参照年月日:2024年12月25日 https://www.alic.go.jp/y-kanri/yagyomu03_000001_00040.html
令和5年国民健康・栄養調査結果の概要 厚生労働省 参照年月日:2024年1月31日 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001338334.pdf
機能性成分 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 食品機能性研究センター 参照年月日:2024年12月25日 https://www.naro.affrc.go.jp/org/nfri/ffrc/katsudo/seibun.html
食品の検査 機能性成分 一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC 参照年月日:2024年12月25日 http://www.mac.or.jp/technical/functionality/
はじめよう朝ベジ! 日本栄養士会 参照年月日:2024年12月25日 https://www.dietitian.or.jp/features/upload/data/20182108_08.pdf