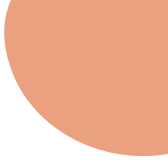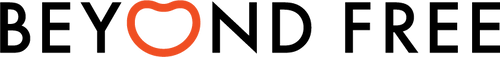中性脂肪を下げる食べ物とその理由を紹介

血液検査の結果で中性脂肪の数値が高くなり、健康面が気になっている方も多いのではないでしょうか?中性脂肪の増加は様々な疾患リスクを引き起こす原因となるため避けたいところです。
この記事では中性脂肪の増加に伴うリスクと減らすメリット、中性脂肪を下げる食べ物について詳しく解説しています。期待できる効果やおすすめの理由も紹介しているため、ぜひ最後まで読んでみてください。
中性脂肪とは

中性脂肪とは私たちの体内にある脂質の一つで体を動かすエネルギー源としての役割があります。内臓脂肪や皮下脂肪など体内に蓄えられる脂肪を総称して「体脂肪」と呼びますが、その大半を占めるのが中性脂肪です。
よく聞く「コレステロール」との違いは何でしょうか?どちらも血中に含まれますが、中性脂肪がエネルギーとして利用されるのに対して、コレステロールは細胞や様々なホルモン、胆汁酸の材料となります。
中性脂肪が増える原因と減らすメリット

中性脂肪の増え過ぎは脂質異常症につながります。脂質異常症は生活習慣が主な原因と考えられているので、以下の項目に当てはまる方は生活習慣を起因とする中性脂肪の増加に気を付けましょう。
・過食
・多量の飲酒
・脂質の摂り過ぎ
・高カロリー食
・運動不足
中性脂肪が多いと脂質異常症だけでなく高血圧や糖尿病にもつながり、それらが悪化すると動脈硬化から脳梗塞、心筋梗塞などの疾患につながるリスクが高くなります。中性脂肪を減らすメリットとして、これらの疾患リスクの軽減があると言えるでしょう。
中性脂肪を下げる食べ物

中性脂肪を下げるための大切なポイントは摂取カロリー(特に糖質・脂質)を減らしたり、それらを減らすサポートをする働きの栄養を摂取したりすることです。
ここからは、中性脂肪を下げる効果が期待できる食べ物を紹介します。
野菜類
野菜はカロリーが低く低脂質のため、摂取カロリーが増える原因になる糖質や脂質を減らしてカサ増しとして取り入れることで、食事全体の摂取カロリーを抑えられます。また野菜には食物繊維が多く含まれており、食物繊維には糖質や脂質を吸着して体外へ排出する働きが期待できます。
食物繊維を含む野菜の例を以下に挙げています。
・玉ねぎ
・アボカド
・大根
・ごぼう
・れんこん
・にんじん
・ほうれん草
・かぼちゃ
・モロヘイヤ
・青ピーマン
野菜の種類や栄養素、摂取量の目安については以下を参考にしてください。
緑黄色野菜とは?定義や淡色野菜との違いなど、一覧で該当野菜をご紹介
野菜1日分の量350gとはどれくらい?無理なく摂取する方法などご紹介
食物繊維の他にも抗酸化物質として知られるフィトケミカルが含まれており、野菜の種類によって含有する種類が異なります。以下の記事ではフィトケミカルの定義や効果、含有食品について解説しているためぜひ読んでみてください。
フィトケミカルとは何ですか?効果や含有する食品など
きのこ類
きのこ類も野菜と同様、低カロリーかつ食物繊維を多く含んでいます。食物繊維は主に水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2タイプに分かれ、きのこ類は特に不溶性食物繊維が多い食品です。
不溶性食物繊維には便のかさを増し便通を整える働きがあると言われています。きのこ類の代表的な種類は以下の通りです。
・エリンギ
・なめこ
・えのきたけ
・ぶなしめじ
・まいたけ
・ひらたけ
・しいたけ
・きくらげ
・まつたけ
・マッシュルーム
水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の違いについて知りたい方は以下の記事をご覧ください。
食物繊維の水溶性と不溶性の違いとは?食品に含まれる割合の一覧も
海藻類
海藻類もカロリーが低く食物繊維を含む食品です。主な海藻製品には次のようなものがあります。
・こんぶ
・わかめ
・のり
・てんぐさ(ところてん、寒天)
・あおのり
・あおさ
・あらめ
・めかぶ
・ひじき
・海ぶどう
大豆製品
大豆製品には植物性たんぱく質が含まれ、肉類や魚類などの動物性たんぱく質に比べて脂質が少なく低カロリーなのが特徴です。調理時に牛肉や豚肉の代わりとして大豆ミート・豆腐・厚揚げなどを使ったり牛乳の代わりに豆乳を使ったりすると、摂取カロリーや脂質を抑えられます。
以下の記事では大豆に含まれるたんぱく質や豆乳の栄養素、植物性由来の代替肉について詳しく解説しています。
大豆のたんぱく質ってすごい?含有量や種類、大豆食品や野菜などとの比較
豆乳の栄養素は種類によって変わる?牛乳・アーモンドミルク・オーツミルクとの栄養素比較も
代替肉とは?どんな種類や商品があるのかをご紹介
発酵食品
発酵食品とは微生物の働きを利用して作られた食品で、腸内環境を整える働きなどがあります。また糖質や脂質ではなく発酵食品のうま味や香りを活かしておいしさを向上させると、発酵食品の種類によりますがカロリーや糖質、脂質の摂取抑制につながります。
食品の例は以下の通りです。
・醤油
・味噌
・ぬか漬け
・キムチ
・納豆
・ヨーグルト
・チーズ
・甘酒
善玉菌を増やすためには継続した摂取がポイントです。
スーパーフード
スーパーフードとは、定義はありませんが、一般的に体に良いとされる栄養素を含む食品や様々な健康効果が期待できる食品を指します。食品によって含有成分に違いはあるものの、抗酸化物質や食物繊維を含むものは中性脂肪が気になる方におすすめです。
ここでは抗酸化物質(ビタミンA・C・Eやフィトケミカル)、食物繊維などを含む食品を紹介します。
・ブルーベリー・アサイー(抗酸化作用のあるアントシアニンや食物繊維を含む)
・ほうれん草・ケール(ビタミンA・Cや食物繊維を含む)
・ナッツ類(不飽和脂肪酸を含む)
・全粒穀物(食物繊維を多く含む)
・いんげん豆などの豆類(食物繊維を含む)
スーパーフードについてさらに詳しく知りたい方は、こちらを参考にしてください。
スーパーフードを一覧で紹介!栄養価や特徴など
アサイーとは何か?気になる味わいや健康機能などを紹介
植物性油脂
脂質は飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分かれ、動物性油脂に多く含まれる飽和脂肪酸を多く摂ると中性脂肪が増えやすくなると言われています。そのため不飽和脂肪酸の多い植物性油脂を選択すると良いでしょう。具体的には以下のようなものがあります。
・オリーブオイル
・大豆油
・こめ油
・ひまわり油
・あまに油
・べに花油
・えごま油
・ごま油
・菜種油
・とうもろこし油
油脂類を上手に取り入れるには普段使っている動物性油脂を植物性油脂に替えてみるのがおすすめです。ただし体に良いと言っても植物性油脂は高カロリーであり、多量に摂るとカロリーや脂質の摂り過ぎにつながるため注意してください。
全粒穀物
米や小麦、ライ麦、大麦などイネ科の植物の種子などを総称して「穀物」と呼んでいます。精製された穀物は胚芽・胚乳・外皮が取り除かれていますが、全粒穀物は種そのものや潰したものが提供されるため胚芽・胚乳・外皮がすべて含まれているのが特徴です。そのため全粒穀物は精製された穀物よりも糖質が低く食物繊維が多い傾向があります。全粒穀物が使用された食品は次のようなものです。
・全粒穀物のシリアル
・オートミール
・全粒小麦パスタ
・全粒穀物クラッカー
・全粒穀物パン
全粒穀物は胚芽や外皮が残っているため食物繊維を多く含みます。精白された一般的な穀類(米や小麦など)の代替として取り入れると良いでしょう。以下の記事では、あわやひえなどの雑穀、オートミールについて食べ方のコツを解説しています。
雑穀とは何ですか?種類や栄養、使い方など
オートミールとは何か?カロリーや糖質など白米との違いを簡単に解説
今日から中性脂肪を下げる食べ物を取り入れよう!

中性脂肪は体を動かすためのエネルギー源として重要な役割を担っていますが、増え過ぎると健康に影響を及ぼすリスクが高くなると言われています。中性脂肪の増加には過食や糖質・脂質の摂り過ぎなどの食習慣が関わっているため、いつもの食事に中性脂肪を下げる食べ物を取り入れるなどして食生活を見直してみましょう。
参考文献
生活習慣病などの情報(e-ヘルスネット) 厚生労働省 参照年月日:2025年7月27日
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/
全国健康保険協会 協会けんぽ 参照年月日:2025年7月25日
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
国立大学法人 千葉大学大学院園芸学研究科 教授 博士(農学) 江頭 祐嘉合 ファイトケミカル・食物繊維の健康増進機能~抗炎症作用~Health Promotion Function of Phytochemicals and Dietary Fiber: Anti-Inflammatory Function 参照年月日:2025年7月25日
https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/105016/S18808824-72-P002.pdf
筑紫野市総合保健福祉センター「カミーリヤ」健康推進課 管理栄養士 参照年月日:2025年7月25日
https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/uploaded/attachment/14899.pdf
公式ホームページ 農林水産省 参照年月日:2025年7月28日
https://www.maff.go.jp/
【監修者】
管理栄養士・和食ライフスタイリスト
合田 麻梨恵

大学卒業後、コンビニ商品開発を経て独立。2万件以上の予防医学に関する論文読破・発酵生産者100軒以上訪問・100名様以上の栄養指導経験を活かし、料理講師やセミナー講師、監修、書籍執筆などを行う。一般社団法人日本和食ライフスタイリスト協会代表理事、「中高年のための食と予防医学」の著者。